



1 「日本で一日でも長く安泰に暮らせるなら、我々がこの島を守る一日には、意味があるんです!」
硫黄島 2005
この日、調査隊が入り、地下壕に埋められた重大な資料を発見する。
硫黄島 1944
「花子、俺たちは掘っている。一日中、ひたすら掘り続ける。そこで戦い、そこで死ぬことになる穴。花子、俺、墓穴掘ってるのかな」
硫黄島守備隊に所属する西郷・陸軍一等兵のモノローグ。
「本日付で私は、自分の兵が待つ任地へと向かう。国の為に忠義を尽くし、この命を捧げようと決意している。家の整理は大概つけてきたことと思いますが、お勝手の下から吹き上げる風を防ぐ措置をしてこなかったのが、残念です。何とかしてやるつもりでいて、ついついそのまま出征してしまって、今もって気がかりであるから、太郎にでも早速やらせなよ」
硫黄島の守備隊を率いる栗林忠道・陸軍中将の機内でのモノローグ。
 |
栗林忠道
「こんな島、アメリカにくれてやろうぜ。そうすりゃ、家に帰れるぜ」
 |
| 西郷(右) |
苛酷な環境で、海岸線の塹壕堀りをする西郷は、思わず同僚に本音を語る。
その話を聞きつけた谷田大尉に、「貴様、今、何と言った!」と詰問されると、西郷は「アメリカに勝てば、家に帰れる」と言い逃れる。

そこに、栗林中将が硫黄島に降り立ち、早速、歩いて島を一周するが、途中、西郷らが鞭で打擲(ちょうちゃく)される現場を見て、谷田を問い質す。
 |
摺鉢山(標高84m)を見る栗林 |
「非国民のような、暴言を吐いていました」
 |
| 谷田大尉(右) |
栗林は体罰を止めさせ、昼飯抜きのペナルティーに変えさせる。
「いい上官は鞭だけではなく、頭も使わんとな」
更に、米軍上陸を水際で食い止めるため、海岸沿いに塹壕を掘っていることを知り、それも止めさせ、兵士たちに十分な休息を取らせるよう指示する。
西郷は、同僚から栗林がメリケンに住んでいたから、メリケン好きで、塹壕を掘らせているんじゃないかと話を聞かされる。
「メリケンの勉強をしておられるんだよ。だから、どうやって打ち負かせるのか知ってるんだ」
 |
| 野崎(左) |
夜になり、栗林は伊藤海軍中尉に、現在、使える航空兵力の残数について質問する。
「戦闘機41機、爆撃機13機であります」
 |
| 伊藤海軍中尉(右) |
「それだけか」
「サイパンの艦隊を援護するため、先日、66機出動しました」
栗林は、海軍が陸軍と情報を共有できていないことを知り、指示を出す。
「速やかに陸軍と連係を取りなさい。まず、摺鉢山の防御が第一です」
栗林が去ると、伊藤は不満を漏らす。
栗林は、島に残る住民たちを本土に戻すよう指示する。
 |
| 島に残る住民たちを見る |
そこに、戦車第26連隊長の西竹一(にしたけいち)陸軍中佐がやって来て、栗林と再会する。
 |
| 西中佐(左) |
西は、オリンピックの馬術競技で金メダルを獲った有名人で、「バロン西」とも言われる。
 |
「バロン西」に金メダルをもたらした愛馬・ウラヌスと共に浜辺を歩く
その夜、二人はジョニーウォーカーを飲みながら、空の皿を前に語り合う。
「しかし、今となっては、連合艦隊の壊滅的打撃(注)は、痛恨の極みですね。戦艦はまだあるにはありますが、もはや我が軍には、制海権、制空権ともなきに同然です」
「どういうことだ、西君」
「やはり、先日のマリアナ沖での一件は、お耳に入っていらっしゃらないんで。小沢提督の空母、艦載機は既に撃退されております」
「大本営は国民だけでなく、我らも欺くつもりなのか」
「正直に申し上げてもよろしいですか、閣下。もっとも懸命な措置は、この島を海の底に沈めてしまうことだと思います」
「それでも君は、ここに来た」
(注)【1944年6月19日、20日におけるマリアナ沖海戦のこと。日米両海軍の空母機動部隊による戦闘で、日本の連合艦隊は、この海戦で壊滅的な敗北を喫し、この地域の制空・制海権を米軍に奪われてしまった。かくて、米軍は日本本土への B-29の空襲を激化させていくに至る】
.jpg) |
| マリアナ沖海戦/アメリカ軍の攻撃を受ける空母瑞鶴と駆逐艦2隻(ウィキ) |
―― 物語のフォローを続ける。
栗林は、米軍が上陸する地点を特定したあと、作戦の変更を部隊長らに言い渡す。
「大きく作戦を変更します。元山(もとやま)、東山、そして摺鉢山(すりばちやま)一帯にかけて洞窟を掘り、地下要塞を構築する。地下に潜って、徹底抗戦だ」
海岸の防衛線は必要ないと明言すると、それでは勝てる戦(いくさ)も勝てないという異論が出る。
「米国が一年間に生産する自動車の台数をご存じか。五百万台だよ。彼らの軍事力と技術力を過小評価したらいかん。米軍は確実に海岸を突破してくる。兵をそこで無駄に失っては勝ち目はない」
それでも、部下たちの反対意見が続く。
「兵隊が死ぬのは致し方ありません。ですが、島の防衛で海岸を放棄するなど聞いたことがない」
「閣下、今から洞窟を掘るなど、無駄な時間を費やすだけです。できる限り誘(おび)き寄せ、空と海から挟み撃ちにするべきです」「私もその意見に賛成です。合理的だ」
そこで栗林は、連合艦隊が壊滅し、硫黄島が孤立したも同然であること、更に、大本営から残っている戦闘機を東京に戻し、本土防衛に就かせるよう命令されたことを話す。
「そんな無茶な。どうしろっちゅうんじゃ!」
「議論の余地はありませんね」
こんな調子だった。
ここで、新たに硫黄島に配属された陸軍上等兵・清水の手紙が紹介される。
「母上、本日か新しい部隊に配属されることになりました。この度の異動については、今はお伝えすることができません。では、お元気で」
元憲兵の清水が部隊に入って来たことで、警戒感が漂う部隊。
 |
| 清水 |
西郷は召集前に、妻とパン屋をして、カステラやあんぱんなども作っていたが、そこに憲兵がやって来て品物を奪っていったと、清水を睨みながら親友の野崎に話す。
そして、道具も何もかも持っていかれた店に、召集令状が届いた日のことを回想する。
「あなたがいなくなったら、私、どうすればいいの?」
「おいおい、俺はまだ棺桶に入っちゃいねぇぞ」
「だって、誰も帰って来ないんだよ。一人もだよ。絶対、返してもらえないのよ」
「大丈夫だって」
「この子だって…」
西郷は花子のお腹に顔を寄せ、花子の手を握りながら、お腹の赤ん坊に声をかける。
「今から言うことは、誰にも言っちゃいけないぞ。父ちゃんは、生きて帰って来るからな」
ここで、硫黄島で惹起している現実に戻る。
洞窟戦に意味がないという海軍少将の大杉は、栗林に潔く死ぬべきだと進言するが、栗林は反論する。
 |
| 大杉海軍少将 |
「日本で一日でも長く安泰に暮らせるなら、我々がこの島を守る一日には、意味があるんです!」
そして、大杉に大本営に速やかに支援部隊を送るよう進言して欲しいと、頭を下げるのだ。
しかし、大杉は栗林に反発したまま島を離れて行った。
それでも意志が変わらない栗林の、厳しく精悍な表情が映し出されるのだ。
2 「諸君、最善を尽くせ。そして、正しいと思う道を行ってくれ。それが己の正義なんだ。いいな」
地図を広げた作戦会議で、谷田大尉が米軍の圧倒的軍事力の優位に対し、米軍にないものは何かと問うと、清水が立ち上がって答えた。
 |
| 谷田大尉 |
「米兵は意志が弱く、日本兵に劣るところであります…米国軍は規律がなく、自分の感情に負けてしまう腰抜けの集団だからであります」
その直後、爆撃機の空襲を受け、守備隊は大打撃を受ける。
米国艦隊がサイパンを出て、硫黄島に向かっていると報告を受けた栗林は、洞窟に籠る兵士たちに向かい、祖国防衛の戦いへの檄を飛ばす。
 |
| 硫黄島に向かう米国艦隊 |
「10人の敵を倒すまで、死ぬことは禁じる。生きて、再び祖国の地を踏めることなきものと、覚悟せよ!」
そこから、各兵士たちは家族に手紙をしたため、写真を整理し始めた。
便器の糞を捨てに外へ行かされた西郷は、洋上に浮かぶ夥(おびただ)しい数の艦隊を目にし、艦砲射撃に晒される。

米軍の海岸への上陸作戦が始まるが、浜を敵兵が埋めるまで攻撃を制止する栗林。

十分引き付けてから、洞窟から攻撃を開始し、一定の成果をあげる。
しかし、摺鉢山が陥落し、玉砕の許可を求める足立少佐に栗林は許さず、何としても生き抜いて、北の伏角(ふっかく)陣地に合流せよと命令するが、「武士の本懐を」と言うや、足立は西郷に自決命令書を差し出し、上官(谷田大尉)に渡せと命じ、自決に振れていく。
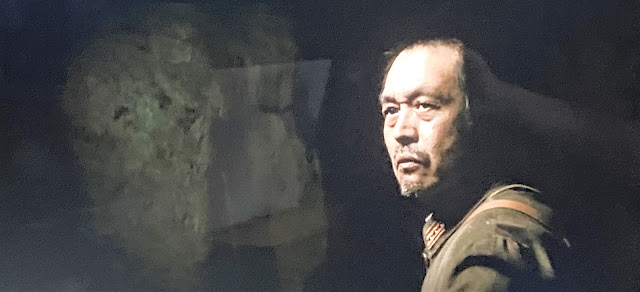 |
| 足立少佐 |
西郷が、谷田大尉に足立少佐の命令書を渡しつつ、栗林の命令を伝えようとするが、谷田に一蹴されてしまう。
 |
| 谷田大尉 |
「我らは、陛下の栄えある皇軍である。そのことを忘れてはならん。残された道はただ一つ。潔い死に様である。これが定めと、靖国に御霊(みたま)となって帰ること。靖国で会おう」
「天皇陛下万歳!」を全員で唱え、各人が次々に手榴弾で自決していく。
 |
| 手榴弾で散っていく野崎 |
親友の野崎も家族の写真を握り締めながら、手榴弾で散っていった。
谷田はピストルで頭を打ち抜き、自決する。
残ったのは清水と西郷。
西郷はその場を離れようとすると、後ろから清水に銃口を向けられ、自決すべきと迫られる。
西郷は清水に対して、無線で聞いた「北の洞窟の舞台に合流しろ」という命令に従うためだと説得する。
「ここでこのまま死ぬのと、生きて戦い続けることと、どっちが陛下の御為になる?どっちだ!」
かくて、拳銃を下ろした清水も、西郷と行動を共にすることになる。
二人は、東の洞窟で合流するようにと命令を受けた別の兵士たちと移動するが、敵の攻撃に晒され、多くの兵が命を落としてしまう。
西郷と清水は、何とか元山の洞窟に残る伊藤中尉の部隊に辿り着くが、そこで摺鉢山から逃げて来たと聞くや、伊藤は激怒する。
「この、愚か者めが!!死んでも山から離れるなという命令だったはずだ。貴様らは、部隊と共に死なねばならぬのだ。恥さらしめが。跪(ひざまず)け!」
跪いた二人は、伊藤の刀で首を討ち落とされる寸前に、栗林が来て、制止する。(このカットは如何にもハリウッド的で頂けない)
「私の兵を無暗(むやみ)に殺してもらいたくないな。刀を下ろしなさい。下ろしなさい!何があったんだ」
生き残った者たちは、北部方面に合流するように命令を下したと栗林は伊藤に語るが、そこで初めて、摺鉢山が陥落したことを知る栗林。
 |
| 陥落した摺鉢山を見る |
「先に逝った仲間たちの為にも、最後まで戦ってくれ」
栗林は伊藤に託すのだ。
ところが、疲弊して横になっている西郷らの前に他の部隊が待ち受け、二人に命じる。
「起きろ!林少将が総攻撃を指揮する。我々は、そこに合流するんだ」
「だが、栗林閣下は洞窟で待機するようにと」と西郷。
「栗林閣下は腰抜けで、アメリカの腰巾着だと、伊藤中尉が言っている」
その直後、兵士を集め、「摺鉢山を取り戻す」と伊藤が命令を下す。
外に出ると、米軍の猛攻撃を受け、撤退を余儀なくされるが、伊藤は、洞窟に残っていた兵士たちに激怒し、胸倉を掴み、「司令官は誰だ!」と怒鳴り散らすのだ。
その場にやって来た西中佐が、それに断然と答える。
「攻撃指令が出ていない」
「何?林旅団長の指令は届かなかったのか」
「栗林閣下が、その命令を撤回された。攻撃は中止と」
「摺鉢山を奪還する。栗林の思惑など知ったことか。既に攻撃は始まってるんだ。さっさと支度しろ」
「自分の立場をわきまえろ!それは、上官に対する反逆だ。その為に兵士が無駄死にしてるのが分からんのか!すぐに持ち場に帰るか、でなければ、貴様の舞台は私が引き継がせてもらう」
「もういい。我々だけでやる」
重大な軍紀違反を犯す伊藤は、そう吐き捨てて、勝手に攻撃に向かうのだ。
部隊を引き連れ、外に出た伊藤は振り返り、部下に言い放つ。
「もう、後には引けん。洞窟での戦はもうたくさんだ。貴様らは西の連隊に合流しろ」
伊藤は地雷を体に巻き付け、一人、敵陣へと向かった。
一方、大本営から伝令が届き、栗林は副官の藤田に読ませた。
「戦局、ここに至りては、友軍を硫黄島に派遣すること、困難極まれり。小笠原兵団は、最後まで敢行し、悠久の大義に生(い)くべし」
 |
| 大本営からの電文(玉砕命令)を読む藤田 |
西は米軍の捕虜に治療を命じ、若い敵兵と和やかに会話をする。


西郷は、清水に語りかける。
「もういい、もうたくさんだ。俺は投降する。捕まえてみろよ。それがお前の任務だろ」
「ここに送り込まれたのは、憲兵隊をクビになったからだ。配属されて、5日目だった…」
清水は、上官と非国民の家を廻っていた際、泣き声がうるさい犬を殺すように命令されたが、子供たちの顔を見て発砲音だけで済ませ、殺さなかったのである。
 |
| 犬を殺せず、憲兵を解任された清水 |
それが直ぐに分かり、上官への反抗罪で除隊になって、硫黄島に配属されたのだった。
清水の吐露を耳にして、西郷は清水への疑念を晴らし、親近感を覚えるのである。
そんな折、捕虜のサムが死に、西がサムが持っていた母親からの手紙を読み上げた。
「サムへ 何冊か本を送ります。気に入ればいいけど…私たちのことは心配しないで。自分の体だけ気をつけて、ちゃんと帰って来てね。そして、母さんの言ったこと、忘れないで。正義を貫けば、それは正義になる。戦争が一日も早く終わり、あなたが無事に戻ってきますように。母より」
読み終えた瞬間、猛攻撃が始まり、西は目を負傷してしまう。
 |
| 目を負傷する西中佐 |
一方、地雷を巻き付けて、戦車の下で爆発させるはずだった伊藤は、いつまで経っても敵は現れず、寝転んで見える空にカラスが舞うのみ。
伊藤は立ち上がり、地雷を捨て、その場を離れていく。
その間、西は大久保中尉を呼び、部隊の指揮官を任じ、残りの弾薬、食料の全てを北部に運び、水を確保するよう命令した。
兵を集め、西は最後の指示を下す。
「諸君、最善を尽くせ。そして、正しいと思う道を行ってくれ。それが己の正義なんだ。いいな」
例の手紙の一節を援用した指示である。
部隊を送った直後、大久保からライフルを受け取った西は、一人残った洞窟で自決するに至るのだ。
3 「もう一つだけ、頼みがある。埋めてくれ。誰にも見つからないように…」
移動する途中、清水が西郷に語りかける。
「西中佐のおっしゃったこと、考えてみた。その通りだ。俺は敵のことを何一つ知らない。アメリカ人は腰抜けだと思ってた。だが、あいつらは違った。鬼畜米英という言葉を、俺は鵜呑みにしていた。だが、あの米兵、あいつの母親の文面は、私の母のと同じだった。私は閣下の為、お国の為に任務を全うしたい。だが、無駄死にはしたくない。西郷、お前はどう思う?」
「なあ、清水。お前は、何かがもったいねぇって思うほど、まだ生きちゃいないんじゃねぇか?」
「西郷、一緒に投降してくれないか?」
合意に達した二人は、早速、実行に移す。
先に、清水が赤痢を装い、洞窟の外に出て行こうとすると、見張りの男が投降すると察し、一緒に出て行った。
それが上官に見つかり、拳銃で撃たれてしまうのだ。
しかし、清水は何とか投降に成功する。
米兵に水をもらい、連れて行かれると、日本人の投降兵がいた。
「メシ、食えるって話だぜ」
投降兵の話に、「メシ、いいなあ」と反応する清水。
ところが、見張りの任務を煩わしく思った米兵の一人が、2人を銃殺してしまうのだ。(2人の日本兵は運が悪かったが、米軍を美化しないこの描写は、とてもいい)
移動する部隊が、死んだ2人を発見する。
 |
| 清水の遺体 |
「捕虜がどうなるのか、肝に銘じとけ」と大久保。
西郷は泣きながら、清水の母親が作った千人針の布を顔に被せた。
敵の銃撃の嵐の中、北部の洞窟へと走り抜ける部隊。
多くの兵が銃丸に斃れた。
大久保は最後に兵士たちが走り抜けるのを助けるため、ライフル銃を乱射し、手榴弾で敵陣に向かい、果てていく。
 |
| 大久保 |
今や、栗林の元に辿り着いた僅かな残党は、栗林の労(ねぎら)いを受けるが、与える水も枯渇していた。
その兵士たちの中に、西郷を見つけた栗林が声をかけた。
「君は見覚えがあるな。あ、首を切られそうになった」
「はい。ですが、あの時、助けていただいたのは、2度目でした。一度目は、閣下がこの島に到着された日のことであります」
「ああ、そうだったか。二度あることは三度あるかもな」
西郷は花子へ手紙を書く。
「花子、この手紙が届くことはないだろう。でも、書いてるってだけで、ほっとするんだ。もう、五日も飲まず食わずだ。ただ、生きるってためだけに、信じられないことまでする。もう、逃げられねえ。でも、お前と赤ん坊のことだけが気がかりだ…」
栗林は、大本営への最後の電文をしたためる。
「戦局最後ノ関頭(かんとう=岐路)ニ直面セリ…茲(ここ)ニ最後ノ関頭ニ立チ 重ネテ衷情(ちゅうじょう=偽りなき心)ヲ披瀝スルト共ニ只管(ひたすら)皇国ノ必勝ト安泰トヲ祈念シツツ…国ノ為重キ努ヲ果シ得デ矢弾尽キ果テ散ルゾ悲シキ」
白襷(しろたすき)を掛けた栗林が、最後の出陣を前に、すべての資料を燃やすようにと、西郷に命じた。
西郷が故郷に、妻と未だ顔を見ぬ娘が残されていると聞き、三度目の救済を図ったのである。
「二度あることは三度ある、だ」
栗林はそう言って、西郷を司令部に残し、洞窟を後にした。
「今より、総攻撃をかける。日本が戦に破れたりと言えども、いつの日か、国民が諸君らの勲功を称える。諸君らの霊に涙し、黙祷(もくとう)を捧げる日が必ずや来るだろう。安んじて国に殉ずるべし。余は常に諸氏の先頭に在り」
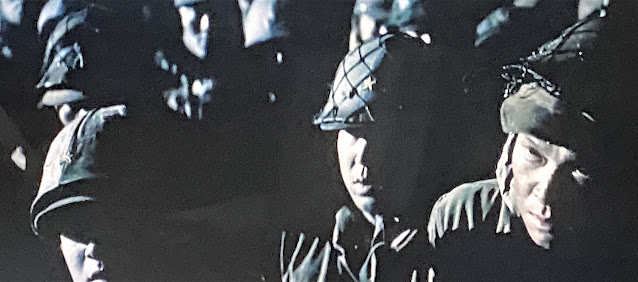
暗闇の中、栗林を先頭に、残り少ない武器で戦いを挑む陸海軍の混成部隊は、米軍からの総攻撃に晒される。
程なく、栗林も砲撃に倒れ、部隊はほぼ全滅する。
行き場を失い、彷徨していた伊藤中尉は、結局、米軍の捕虜となる。
藤田に運ばれて来た栗林は介錯を頼むが、藤田は米兵の銃に撃たれて死んでしまう。
 |
| 介錯を求める栗林 |
遠くから、倒れている二人を見つけた西郷が、栗林の元に駆けつけた。
「もう一つだけ、頼みがある。埋めてくれ。誰にも見つからないように…」
栗林は海を見つめ、アメリカからの帰途を回想するのである。
「太郎、もうすぐ帰ります。日本に帰れるのは嬉しいですが、友人たちとお別れするのは、少し悲しく思います。運転して帰りました。でも、独りぼっちのドライブは寂しいもんです」
栗林は、アメリカの友人にもらった拳銃を手にし、西郷に訊ねる。
「ここはまだ、日本か」
「はい。日本であります」
栗林は残った力を振り絞って胸を撃ち、自決する。
涙を零す西郷は、直ちに栗林を埋葬した。
同時に米兵がやって来て、西郷を見つけ出す。
西郷は、一人の米兵が栗林の拳銃を腰に差しているのを見つけ、憤怒を抑えられず、スコップで暴れるが、後頭部を殴打され、倒されてしまう。
かくして、西郷は捕虜となった。
硫黄島の夕陽を見る西郷。
硫黄島から生還したのである。
―― ここで映像は、ファーストシーンに循環する。
2005年の硫黄島。
硫黄島協力会(正式名称は「日本戦没者遺骨収集推進協会」)は、硫黄島で散った兵士たちの、大量の家族に宛てた手紙を発見したのである。

4 「自決の思想」を否定する男の途切れることのない闘争心がフル稼働する
理が非でも、反戦映画の批評を書きたくなった。
2022年、国際社会のリアルな状況を目の当たりにして、イーストウッド監督の反戦映画の名画を観直し、かつて以上の大きな感銘を受け、8.15(注)に合わせて批評を起こした次第である。
 |
| ウクライナ侵略 2022 |
【注/太平洋戦争を公式に終了したのは8.15(ポツダム宣言受託日)ではなく、米戦艦ミズーリ号での降伏文書に調印した9.2である。実質的に、この日が終戦の日】
 |
ミズーリ艦上で降伏文書の調印に臨む日本側全権団。中央の燕尾服姿が重光外相。【AFP=時事】
―― 以下、批評。
この反戦映画の成功は、以下の4点に集約されると考えている。
その1 「英雄譚」にしなかったこと。
その3 戦争の悲惨さを殊更(ことさら)誇張し、情緒に流さなかったこと。
その4 「自決の思想」・「玉砕の思想」を物語のコアに据えたこと。
「英雄譚」について言えば、民間人を巻き込む愚を犯さなかった栗林忠道を優れた軍人・人格者として描いても、「硫黄島の英雄」と称える人物にしなかったこと。
その栗林を演じた渡辺謙。
彼以外に栗林を演じる俳優はいないと思わせる、リアルな演技に感服する。


その2
二宮和也が素晴らしい演技を見せたパン屋の主人・西郷の視線が全篇を貫流していて、生還することのない絶望的な「戦争」の渦中で煩悶し、迫る来る死に「生活者」として恐々と対峙する感情の漂動が物語を覆っていたこと。
 |
| 「父ちゃんは、生きて帰って来るからな」/西郷には、この思いが常にある |
 |
| 戦友の死に衝撃を受け、遺体に千人針の布を顔に被せる |
要するに、イーストウッド監督の問題意識が、西郷の感情の漂動のうちに表現されていたのである。
また、情緒に流さなかった典型的なシーンがインサートされていた。
死んだ捕虜が残した、母からの手紙をバロン西が読むシーンである。
「戦争が一日も早く終わり、あなたが無事に戻ってきますように」
この手紙の一節を耳にする日本兵の心を震わせ、自然に立ち上がり、捕虜になったアメリカ人が「鬼畜」とは無縁である現実を見せつけられ、動揺したのも束の間、この映画は米軍からの攻撃に晒されるシーンに切り替えていくのだ。
 |
| 手紙の一節を耳にして、自然に立ち上がる西郷たち |
だから、瞬時にトランジション(転換)が行われることで、自然に立ち上がった日本兵が、心の動揺を引き摺るシーンを完璧に削り取っていく。
このシーンも、とても良い。
そして、この映画の白眉は、日本軍の「自決の思想」・「玉砕の思想」の是非について、かなり踏み込んで描いていて、イーストウッド監督の問題意識が垣間見えるようだった。
―― 以下、本稿は、その一点に批評の焦点を当てて考察したい。
「私は硫黄島に行った時、手榴弾で自決したとされる場所に行きました。私には硫黄島で戦った兵士としての経験はないので、理解するのはとても難しく、そのむなしさは全く理解できません。敵に殺されるよりは死んだ方が良いという考えだったのでしょう。でもこれを理解するには、通常とは全く違う精神状態が必要だと思います。なぜそのようなことをしたのかという興味深い疑問を観客に投げかけています」
 |
| クリント・イーストウッド監督 |
イーストウッド監督のインタビューのこの言葉の中に、「敵に殺されるよりは死んだ方が良い」という日本守備隊の「自決の思想」への疑問が率直に語られている。
そもそも、「自決」とは何か。
「指導者が責任を取って自殺すること」という風に書かれているが、そこに「潔さ」を重んじると言われる日本人の「精神主義」が張り付いているから、時として「美学」にまで昇華する。
この「自決の思想」が、玉のように美しく砕け散る「玉砕」の「美学」に膨れ上がってしまえば、「精神主義」の極点になるから厄介なのだ。
アッツ島の日本軍守備隊が全滅(1943年5月)した際、大本営が国民に及ぼすネガティブな影響を軽減するために、「全滅」という言葉を「玉砕」という表現に変換したのがルーツであるが、そこには、守備隊への援軍・補給を行わず、見殺しにした軍上層部の責任を回避させる姑息(こそく)な手法が見え隠れする。
 |
| アッツ島の戦い/日本軍は工兵隊の丘で全滅した(ウィキ) |
 |
| アッツ島の戦い/アッツ島を守る日本軍の高射砲(ウィキ) |
 |
| 「玉砕」という言葉が当時の新聞に掲載されている |
 |
| アッツ島 |
これは、婦女子の断崖からの飛降り自殺に止(とど)めを刺すように、マリアナ沖海戦での敗退によって日本艦隊が制海権を失ったことで、日本守備隊の残存兵力が「玉砕」攻撃を行なって壊滅したサイパンの悲劇(1944年6月)を想起すれば、「玉砕の思想」が「美学」と無縁であることは自明である。
 |
| バンザイクリフ(サイパンの悲劇)/追い詰められた日本兵や民間人が身を投じて自決した悲劇の断崖(ウィキ) |
 |
| サイパンの戦い/水際にむき出しのまま設置されて撃破された日本軍短二十糎砲、奥にはコンクリート製のトーチカが見える(ウィキ) |
 |
| サイパンの戦い/日本軍の激しい攻撃の中でサイパン島に上陸するアメリカ海兵隊 |
そして、パラオ諸島のペリリューの戦い(1944年9月)。
.jpg) |
| ペリリューの戦い/反撃に失敗して撃破された日本軍95式軽戦車、奥は一式陸上攻撃機の残骸(ウィキ) |
1万人以上の戦死者、生還兵が僅か34人という数字に絶句する。
ペリリューの痛ましさは、洞窟の中の地獄で生きたまま埋め殺された兵士たちの声が封殺された歴史を刻む、典型的な玉砕戦の産物だった。
 |
| ペリリュー島 |
同時に、この消耗戦が米軍に甚大な被害を与えることで、日本軍に対する米軍の認識を変え、このペリリューの戦いが硫黄島戦と沖縄戦の苛酷な前哨戦と化していくのだ。
玉砕戦法の非合理性だけが生き残されていくのである。
映画の中でも、玉砕を否定する栗林に異を唱え、足立少佐が谷田大尉に「自決命令書」を出し、谷田が率いる機関銃中隊の兵士に自決を命じ、抗う術(すべ)もない兵士らが手榴弾で死んでいく凄惨なシーンが描かれていたが、このシーンに凝縮されるのは「玉砕」の「美学」の自壊だった。
 |
| 「自決命令書」を出し、自らも自決する足立少佐 |
 |
| 部隊全員に自決を命じる谷田大尉 |
大体、「自決の思想」の根柢にあるのは、勝ち目のない戦争で、逃げ場がなく追い詰められた絶望感と、自分だけが生き残れないという日本人的な同調圧力の心理学である。
この救いのなさは、沖縄戦での「集団自決」の悲劇で炙り出されるが、これを、潔さを重んじる日本人の精神主義と結びつけるには無理があり過ぎる。
 |
| 【チビチリガマ (読谷村指定史跡/ガマとは洞窟)/チビチリガマには140人近くがいた。読谷村に上陸した米軍はチビチリガマに迫った。ガマの入り口に米兵が現れるとガマの中にいた3人が竹槍を持って外の米兵に向かって行き、2人が死亡。ガマの中が騒然となった。武器一つ身につけていない米兵がガマの中に入って来て、投降を呼びかけ投降勧告ビラを残していった。米兵が去った後、在郷軍人がビラを人々から取り上げて回収するや自ら火をつけるが、それを消火する女性らの中でパニックが起こり、最終的に毛布などに火がつけられ、焼死するに至った。自決した83人のうち半数は12歳以下の子供だった/ウィキ参照】 |
 |
| チビチリガマの集団自決跡/沖縄戦で住民80人以上が「集団自決」(強制集団死)に追い込まれた |
「玉砕」の「美学」という観念系には、「どうせ死ぬのなら、自決して早く楽になりたい」という心理が垣間見えるからである。
この「自決の思想」・「玉砕の思想」を否定し、戦争継続を訴えて闘い切ったのが、日本守備隊の司令官・栗林忠道だった。

玉砕を喚いた挙句、捕虜になる伊藤中尉の闘いの顛末(てんまつ)に記号化されているように、その栗林を「腰抜け」扱いする将校たちと一線を画し、絶望的な状況下にあっても、最後まで闘い抜く闘争心に溢れていた。
 |
| 【「総攻撃」のシーンを「英雄譚」にせず、あっさり描いている辺りが、反戦映画として高く評価する所以である。最後までアクション映画にしなかった本篇が、登場人物の心理の振れ具合を丹念にフォロ―する物語として切り取っていたこと。これが何より素晴らしい】 |
「玉砕の美学」を声高に叫び、絶望的な状況下に捕捉されてしまえば諦念が膨張し、「早く楽になる自決」に振れる者たちの闘争心の脆弱さこそ露呈されるのだ。
―― ついでに書いておきたい。
民主派の活動家を死刑執行し、国軍の弾圧に終わりが見えないミャンマーで、銃を取る若者たちが自衛組織を立ち上げ、少数民族武装勢力とも連携しながら抵抗を続けている。
 |
山の中で食事を取るKNDF(カレンニー国民防衛隊)の若者たち=KNDF提供
普通の暮らしから戦闘に踏み込んでいく若者たちが主唱するのは、国軍からむしり取られた民主主義の奪回。
だから、今でも多くの一般市民を虐殺している国軍と闘っている、ミャンマーの若者の闘争心の強靭さに魂が揺さぶられる。
 |
マグウェ地域で国軍を相手に戦うPDF(国民防衛隊)の若者たち=PDFの男性提供
そして今、核大国が主権国家に対して侵略するという暴挙が起こっている。
その核大国に降伏せず、今なお闘い続けるウクライナ人民。
 |
| 怒れるウクライナ市民たちが丸腰でロシア戦車に立ち向かっている |
 |
| 武装していてもいなくても、ウクライナの女性は自分の国を守る |
まさに、侵略され、強奪されても、決して萎えることがないウクライナの人々のスピリットにこそ、最後まで闘い抜くという闘争心(注)の根幹を見せられて、心が震える。
 |
(注)82%の人が「たとえ戦争が長引いたとしても領土を手放してはならない」と答えている。
5 「硫黄島の戦い」とは何だったのか
米軍の戦傷者数の合計実数が日本軍を上回った稀有な戦い ―― それが「硫黄島の戦い」だった。
.jpg) |
| 硫黄島に上陸するアメリカ軍第4海兵師団(ウィキ) |
現在、小笠原諸島の一つである、この激戦の地は、1944年6月、米軍の空襲によって村落が壊滅し、疎開が実施されるまで6集落が存在し、島民の大半は硫黄採取鉱業(硫黄の堆積物の島)、各種の栽培農業や沿岸漁業等で生計を立てていた。
 |
| 硫黄島 |
しかし、日本軍の爆撃経由地として、マリアナ諸島(サイパン、テニアン、グアム)からのB-29の出撃の障壁になった硫黄島を米軍が戦略的重要拠点地と認知したことで、その風景が一変する。
 |
| B-29/最大搭載量9トン・長距離飛行能力を誇る大型爆撃機。日本本土への無差別爆撃を実施した(ウィキ) |
このことは、日本軍から見れば、硫黄島を米軍に対する迎撃拠点にすることのメリットがある。
かくて米軍は、1945年2月19日、硫黄島の完全制圧を目論み、実行に移す。
しかも早急に実行する。
「5日間で完遂する」と言うのである。
のちに3万人近い戦傷者を出したことで解任の憂き目を見る第56任務部隊の司令官、ホーランド・スミス中将の威勢のいい言辞である。
 |
| ホーランド・スミス(ウィキ) |
根拠は充分だった。
既に米軍は、制空権と制海権を掌握し切っていたからである。
確かに、米軍の攻撃は凄まじかった。
爆弾・ロケット弾・砲弾などの猛攻で、地形を変容させるのだ。
日本軍を沈黙させたら、水陸両用の戦闘部隊・海兵隊を上陸させる。
この米軍の戦略を、硫黄島の守備隊を率いる栗林忠道陸軍中将は、全て読み切っていた。
 |
| 「国の為重き務を果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき」という辞世の句を残して55歳で散った、有能な軍人・栗林忠道陸軍中将(ウィキ) |
在米日本大使館の駐在武官を務めた経験があり、日米両軍の戦力の桁外れの差異を知悉(ちしつ)していたからである。
だから、日本の守備隊の戦法の選択肢には、全長18kmにわたる地下坑道を島全体に縦横に張り巡らせて、島全体を要塞化する以外になかった。
 |
| 地形巧みに利用して構築された日本軍トーチカ、このような陣地が島中に無数に構築された(ウィキ) |
 |
| 硫黄島で日本軍が作った貯水タンク(ウィキ) |
そこでゲリラ戦を遂行する。
持久戦に持ち込むことで、徹底抗戦を繋いでいくのだ。
洞窟内に充満する硫黄ガスと焦熱の防御のために、防毒マスクの着用は不可欠だった。
それでも、この「洞窟陣地」でのゲリラ戦は奏功する。
「日本兵はなかなか死ななかった。地下要塞にたてこもった兵士を沈黙させるためには、何回も何回も壕を爆破しなければならなかった。……ある海兵隊の軍曹は、一人の日本兵を殺すのに21発の弾丸を射たねばならなかった」(「硫黄島に救援が来なくても…『太平洋の防波堤』になった男たち」より)
米軍は日本軍の地下陣地を発見するや否や、洞窟の入り口から火炎放射と爆弾を投げ入れる「馬乗り攻撃」と呼ばれる戦術を多用するが、その完全制圧は容易ではなかった。
それでも、1時間に約10mというスピードで、着実に前進を重ねる米軍は、遂に6人の海兵隊員によって、摺鉢山の頂上に星条旗を掲げるに至る。
 |
| 上陸前に摺鉢山に向けて艦砲射撃をおこなうアメリカ軍艦隊(ウィキ) |
 |
| 第26海兵連隊第1大隊の上陸後の戦闘の様子(ウィキ) |
 |
| ジョー・ローゼンタール(米国の著名なカメラマン)が撮影した『硫黄島の星条旗』(ウィキ) |
2月23日の早朝のことだった。
対米開戦にも批判的で、日本軍伝統の「水際作戦」と、アッツ島守備隊の全滅以降、大本営発表で用いられた「玉砕戦」の非合理性を捨てた栗林忠道にとって、大本営の援軍派兵だけが唯一の作戦展開の手立てだったが、大本営は最後まで沈黙する。
以下、3月16日、大本営に送った栗林の訣別の戦訓電報(戦闘状況を大本営に報告する一連の電報)の一文。
「……今ヤ弾丸尽キ水涸レ 全員反撃シ最後ノ敢闘ヲ行ハントスルニ方(あた)リ 熟々(つらつら)皇恩ヲ思ヒ 粉骨砕身モ亦(また)悔イズ 特ニ本島ヲ奪還セザル限リ皇土永遠ニ安カラザルニ思ヒ至リ 縦(たと)ヒ魂魄(こんぱく=神霊)トナルモ誓ツテ皇軍ノ捲土重来(けんどちょうらい=巻き返す)ノ魁(さきがけ)タランコトヲ期ス……」(同上)
胸を衝く。
そして、海兵隊を硫黄島から次第に撤退させていた米軍の警戒が緩んできた3月26日。
緻密に指揮された周到な「総攻撃」が敢行される。
 |
| 日本軍守備隊による3月26日の総攻撃後の状況(ウィキ) |
 |
| 太平洋戦争で米軍にとって最も苛酷な戦闘となった硫黄島の戦いは、1945年2月19日から36日間にわたって続き、この島の拠点を壊滅させた |
 |
| 面積約24平方キロの島を制圧するため、多大な犠牲が払われた |
栗林忠道陸軍中将は、「進退窮まり、最後に『屍は敵に渡してはいけない』と言い残して、近くの洞窟で自決した。満53歳没。…ただし、栗林の最期については、直接見た者は生存していない」(Wikipedia)
「沖縄戦」がそうであったように、そこに繋ぐ「硫黄島の戦い」は、大本営にとって、「太平洋の防波堤となる」と言い切り、それを実践躬行(じっせんきゅうこう)して斃れていった栗林の緻密な作戦など興味なく、知ったことではなかったのである。
 |
| 1937年に設置された大本営陸軍部(ウィキ) |
.jpg) |
大本営陸軍部による発表(ウィキ)
 |
| 大本営海軍部による発表(ウィキ) |
栗林の守備隊それ自身が、本土決戦までの時間を稼ぐだけの「捨て駒」に過ぎなかったのだ。
 |
| 大本営からの電文(玉砕命令)を読む藤田副官/映画より |
「約束された悲劇」を括り、その遺骨も見つかっていない男が近年、皮肉にもハリウッド映画を通して復活したのである。
(2022年8月)
.JPG)

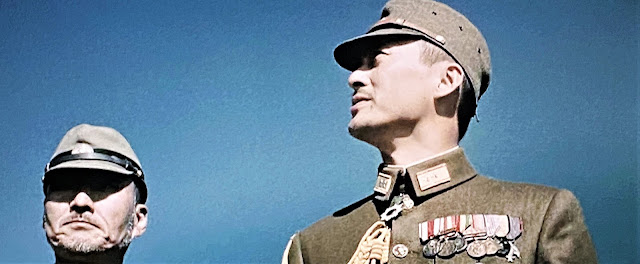























.JPG)







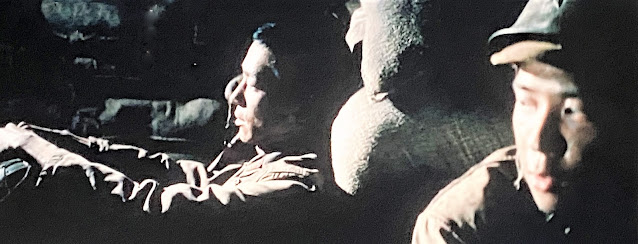






























.jpg)





先日、硫黄島からたった一人帰還の命を受けた人の報道映像を見ました。(硫黄島の戦い 100歳の告白)
返信削除修理した時計が栗林中将の物だったのでは?と想像されていましたが、帰還の理由は告げられなかったそうです。
それから数十年、自分だけが帰還してしまった事を家族にも話さず、帰還出来た理由も分からず生きていく事は大変だったと思います。
102歳になり、硫黄島を再び訪れる事になりますが、その時の表情に重みがあり、なんとも言葉に出来ません。マルチェロヤンニ
この原稿を書きながら、私は「ウクライナ侵略」のことを考えていました。
返信削除硫黄島の戦いと同様に、ウクライナの人々には逃げ場がないのです。
だから、侵略されたら戦うしかないのです。
当初、戦うことなく停戦を呼びかけるコメンテーター、専門家らがいたが、彼らの脳裏には「プーチンの戦争」の意味が全く分かっていないから、厄介でした。
「プーチンの戦争」の本質が、停戦=国民国家の解体であり、ジェノサイドであること。
戦う以外の選択肢がないのは、クリミア併合という、一方的な力による現状変更の領土略奪を、国際社会が安易に認めてしまった失敗を繰り返さないためです。
西側の継続的援助と継続的国際世論によってのみ、「プーチンの戦争」に対峙する。
最終的に、プーチン体制の崩壊にまで及ばない限り、「目的のためには手段を選ばず」という絶対ルールで生きてきた男の戦争を止めることができないと、私は考えています。
コメントありがとうございます。