<恋の風景の縺れた糸の行方>
1 夜中まで恋バナを咲かせて、盛り上がる二人
物語の舞台は、【古着屋・古本屋・飲食店・商店街・映画&若者の恋模様】として、映画の中で記号化される下北沢。
 |
| 【下北沢】古着屋 |
 |
| 【下北沢】古本屋 |
 |
| 【下北沢】飲食店 |
 |
| 【下北沢】商店街 |
 |
| 【下北沢】映画館・トリウッド(ウィキ) |
二人の男女がいる。
主人公・荒川青(あお。以下、青)と恋人・雪(ゆき)の若者である。
以下、二人の会話。
この日は、雪の誕生日だった。
「誰、俺の知ってる人?マジ、誰?ホントに、ホントに」
「それは言えない」
「何で?」
「だって、相手に迷惑がかかるから」
「え、何なの?何で、そっちの味方なの?マジ、誰?」
 |
青(右)と雪
「しつこい」
「お前が悪いんだからね。このままじゃ、許すに許せないよ」
「うん」
「え、いいの?」
「うん」
「いいの?許せなかったら、別れるしかないんだよ」
「うん、別れたい」
「別れたいの?」
「うん、別れて欲しい」
「いや、あのさ、自分が言ってること分かってる?」
「うん、分かってるよ。私が浮気して、全部して、許してもらえないし、別れたい」
「俺は、別れたくないよ」
「私は、別れたい」
「今、あなたの気持ちは聞いてないです…絶対、別れないから」
「何で?許せないんでしょ?」
「え、何なの?自分が浮気しておいて別れたいって…絶対、別れない」
「じゃ、それでいいよ」
「え?」
「私は別れたと思って明日から過ごす。その人とちゃんと付き合う。あなたは別れてないと思って、彼女がいるって言い続けたら?私が彼女だって言い続けていいよ。明日からも」
「斬新すぎるわ…」
ここで、青を射程にする雪の視線が固まり、沈黙が流れる。
結局、完璧に振られた青は、雪に「帰って」と言い放ち、彼女は黙って出ていく。
一転して映し出される、古着屋に勤める青の視線の落ち着きのなさ。
店が終わると、ライブハウスの弾き語りを聴き、その足で行きつけのバーで飲みながら、マスター、常連客と他愛のない会話をする。
古本屋へ行くと、店員の田辺冬子(以下、冬子)から声を掛けられた。
「荒川さんて、元々音楽やってたって、本当ですか?」
「え、何で?誰から聞いたの?」
「店長から」
「カワナベさん?え、いつ?」
「亡くなる前に」
「そりゃ、そうだよね。亡くなったら、聞けないから。そんな話、したことあったかな、カワナベさんに」
「え、どうなんですか?やってたんですか?音楽」
「やってたって、遊びでね。大学の時に。何か、みんなやるでしょ、そういうの」
「バンドですか?独りですか?」
「独りです…友達いなかったから」
「え、じゃあ、曲とかも作ってたんですか?それとも、カバー?」
「カバーもしてたし、何曲か作ってましたね」
その後、自分で作った『チーズケーキ』という歌の説明をする青。
ここまでワンカット。
本の清算をしてもらいながら、青が尋ねる。
「あのさ、田辺さんって、カワナベさんとできてたの?」
唐突過ぎた。
この一言で冬子は固まり、無言のまま、奥に引っ込んでしまう。
 |
| 冬子 |
気まずい思いで店に戻った青は、古本屋に電話をかけ、留守電に謝罪の言葉を入れる。
「田辺さん、先ほど、ホントに失礼しました。多分、昔、音楽をやっていたこととか、そういうこと聞かれて、気が緩(ゆる)んだというか。僕にとってのそれは、不倫とか、そういうことの秘密と同じくらい、アレって言うか、センシティブな…」
自らの思いを表現し切っていた。
ある日、店に高橋町子(以下、町子)という美大生がやって来て、卒業制作の自主映画の出演を青に依頼してきた。
 |
| 町子(右) |
監督をしている町子は、青に読書をしている姿を撮りたいと言って、脚本を置いていく。
最初は断った青だが、自分の読書シーンを携帯に撮って、練習するのだ。
 |
| 普段着ではない服を着て練習する青 |
冬子の店に行き、留守電を聞いていないというので、その場で再生してもらう青。
 |
| 留守電を聞く冬子 |
「こちらもすみませんでした」
そう言うや、冬子は青の思いを素直に受け取り、青の撮影練習を手伝うことになる。
青の店で、本を読む姿がぎこちなく不自然なので、冬子が本を持って、読んでいるところを撮らせて見せるのだ。
その本の間から、カワナベに振られた女性からカワナベを非難するメモが落ちて、それを読んだ冬子は、青に吐露する。
「もし、僕が結婚していなくても、付き合ってくれたって言われことがあるんです。僕が結婚してなくても、僕に魅かれたって?生きてるときに、店長に。私、そういう人とばっかり、付き合ってたから。結婚してる人にしか魅かれなくて…」
「そうだったんだ…」
「アイツ、バッカみたい。辛かったろうな…」
そこで青は、古本屋の留守録に残るカワナベの音声を聞かせるのである。
青の優しさが印象付けられるが、一歩間違ったら相手を傷つける危うさもある。
撮影当日。
青は控室に案内され、出演者の連ドラの俳優・間宮武(まみやたけし)に、元カノ(雪のこと)が大ファンであることを話す。
 |
| 間宮(左) |
そこまでは良かったが、撮影で緊張する青のカットは何度も撮り直された挙句、他の者(スタッフ)と交代させられることになる。
 |
| 緊張して、何カットも撮らされるが、交代させられる |
控室に監督の町子がやって来て、青のシーンを使わないことを言い難(にく)そうにしていた。
「ほんと、あれだったら、全然使わなくても大丈夫です」
「ホントですか?良かったぁ。多分使わないことになりそうで。今、それを伝えに来たんです。せっかく出てもらったのに、すみません」
「あ、でも、もしあれだったら、映像見てから判断してもらってもいいですよ。今、決めなくても。いや、どっちでも。全然アレなんですけど、撮った映像をチェックしてからでも…」
「しました!しました、チェック」
「済(ず)み?もう、チェック済みで、使わない?」
「はい!済みです、済みです」
「済み?」
「あ、でも、繋いで考えてみますね」
さすがに気が引けた町子は、一旦、出ていくものの戻って来て、控室に一人残され、落ち込んでいる青を飲み会に誘った。
映画論から恋人の話題に及んだばかりか、青にオファーを出した失敗にまで議論が進み、すっかり盛り下がった空気を感受し、スタッフ同士の飲み会に入っていけず、店の片隅に座っている青の横に、衣装スタッフの城定(じょうじょう)イハ(以下、イハ)が隣に座り、話しかけてくる。
 |
| 「何でよくわからない古着屋なんかに頼んだの」(スタッフ)という言葉が、青の耳に入ってくる |
 |
| イハ(右) |
二人とも「アウェイ」ということで、2次会には行かず、控室として使われているイハのマンションで、夜中まで恋バナを咲かせるのだ。
「…僕は雪との馴れ初(そ)めから、彼女がどんな人だったか、そして、浮気されたのに振られたことなど、すべてを話した。イハにはなぜか、その話をしてもいいと思えたし、引き摺っていることも素直に話せた」(青のモノローグ)
今度は、青がイハの恋バナを聞き出す。
「今まで付き合った人は、3人おるんやけど、最初の彼氏の話はいいや。特になんか、話すことないから」
「え、何でよ?」
「いいねん、いいねん。2人目の人の話していい?その人のことが、まだ好きなんやけど」
「じゃ、おかしくない?3人目の人は?」
「そんな、好きちゃう」
「え、けど、付き合ったの?」
「うん、うん、え、なに?そういうときもあるやん、あかんの?」
「あかんくないけど、好きじゃないなら、付き合わなきゃいいのに」
「え、いや、そんなさ、なかなかキレイに行かなくない?そんな、うまく寂しさコントロールできんよ」
「まあ、そうか」
イハは2人目に付き合っていた、まだ好きだという幼馴染の関取の話をしたあと、こう切り出す。
「何でそう、男と女はさ、いや、別に同性でいいんやけどさ。付き合ったり、好きって思ったりせんかったらさ、こうやって何でもしゃべれる話せるやん。けどさ、いざ、異性として意識するとさ、嫉妬したりとかさ、いつもおもろく喋れてる話がつまらんかったりするやん」
「確かにね」
「何か、こういう距離感のまま、付き合っていくことって、できへんのかなって、いつも思う」
「でも、嫉妬とか、そういう感情がなくなったら、何かつまんない気もするけどね。ある種の証拠っていうか」
こんな会話が長々と続いた後、お茶を取りに行ったイハは、青に言う。
「友達になって欲しいかも。友達おらんし、私」
「あ、是非」
途中、風俗の話から始まった10分間のワンカットシーンは、ここで閉じていく。
夜中まで恋バナを咲かせて、盛り上がった二人。
イハと出会った青の気分が浄化されていくようだった。
2 恋の風景の縺れた糸の行方
雪の相手が明らかにされるシーンが挿入される。
相手は町子の自主映画の撮影に出演し、青が控室で声をかけた朝ドラ俳優の間宮武だった。
その間宮に、別れ話を告げる雪。
「本当のこと言うね…楽しくないの。一緒にいても、楽しくないの…気、使うし、二人のバランスが悪くて」
「そんなの、勝手にそっちが、そうなってるだけじゃん。別に普通に、リラックスしてればいいじゃん」
「それができないから別れたいの。一緒にいるのが辛いの…ごめん」
「え、俺のこと、好きは好きなの?」
「好きだよ。好きだから、辛いんじゃん」
「だったら、いいじゃん。一緒にいてよ」
「ごめんなさい…間宮君と付き合って分かったの。前の彼氏が、いかに居心地が良かったかって…そっちの方が私には楽しかったの。もう、遅いけど」
「もう、遅いけど」と言う雪の表情には、失ったものの大きさを悔いる感情が膨張し、それを復元できない心の負荷が張り付いているようだった。
一方、イハの3人目の彼氏の話に及び、夜中になった青は、イハの家に泊まることになるが、特に何も起こらない。
見送りに来たイハを歩く青の前に、飲み屋のマスターと一緒に歩く雪と遭遇し、驚く青。
コントのように挿入されるこのシーンで明らかにされたのは、青に対する自分の思いを上手に表現できない雪の封印された感情だった。
以下、コントの応酬。
「言ってた浮気相手ってマスターなの?」と青。
「そんなわけないじゃん」と雪。
「今まで店で飲んでて、朝になっただけ」とマスター。
「そんなわけないじゃん。今、何時?」と青。
「青こそなんだよ。あれだけヨリ戻したかったのにさ。いるじゃん彼女」とマスター。
「彼女じゃないから。昨日、知り合ったばっかだし」と青。イハを指差す。
「そうなの?」とマスター。
「ハイ。昨日、知り合ったばっかです。ウチ泊ったけど」とイハ。
「いや、余計なこと言わなくていい」と青。イハを制する。
「でも、ほんまにです」とイハ。
「そう、何もないよ」と青。
「聞いてないし。どっちでもないし」と雪。
「てか、マスター。汚いっすよ、マジで。どうなの、そういうの!あり得ないよ!」と青。声を荒げてしまう。
「だから、違うって。一回、聞いて」とマスター。
「聞きますよ。ハイ、何すか?」と青。
「雪ちゃん、ホラ」とマスター。雪を促している。
「いや、いいです…」と雪。口ごもっている。
「いや、言ったほうがいいって、ちゃんと」とマスター。
「間」の中から、雪がネガティブな言辞を吐き出した。
「あたし、青と付き合っている時に、一回殴られたんですよ」と雪。
この雪の言葉に対して、「どっちが先に殴ったか」という押し問答が続き、収拾困難になった。
更に、状況を悪化する事態が起こる。
イハが別れたがっている3人目の彼氏が出現し、イハのアパートの鍵を「これ」と言って渡すのである。
「俺の分まで、イハのこと、幸せにしてください」
驚愕する青に向かって、雪は言い放つのだ。
「やっぱり、彼氏じゃん」と雪。
「いや、彼氏です」とイハ。別れたがっているから、そう言うのである。
もう、収拾不能になった。
この混乱の渦中で、マスターが明言する。
「雪はね、青とヨリ戻そうとしててね」とマスター。
驚く青。
それを否定する雪。
「これだけはちゃんと聞かせて」と青。真剣になっている。
雪の本音を問うていくのだ。
それに答えず、雪はイハの3人目の彼氏が乗って来た自転車で、その場を去っていくというオチになった。
青は、雪の想いを察知できないでいるが、このコント風絡みの只中で知らされる雪の真情に近づく伏線になっていく。
青は自分のアパートでかつて弾いていたギターを取り出し、自作の「チーズケーキ」を弾き語りする。
自力で解決し得ない様々なことが通り過ぎていったが、少しは前向きになった若者の時間が動いていくようだった。
時間が動くと、主体を囲繞する景色も変わっていく。
雪が間宮を連れて訪ねて来たのは、その直後だった。
相手が間宮であると知り、驚く青。
「雪の元カレって、この人?」
「うん」
「会わしてくれて、ありがとう。さようなら」
その状況を見ていた青は、慌てて出ていった間宮に声をかけ、雪に対して、「追い駆けなよ。凄いことだよ。間宮武だよ!」と叫ぶのだ。
「バカ。本当にバカだね、青は…好き」
 |
| 絶句する青 |
この雪の一言で、恋の風景の縺れた糸の行方が軟着したのである。
一方、町子の自主映画の上映後、それを観に来た冬子が、町子に問い質す。
「何で、荒川さんの出演シーン、全部カットしてしまったんですか?荒川さん、滅茶苦茶、一生懸命練習してたんですよ。何で、カットしちゃったんですか?」
冬子は青の本を読んでいる姿を携帯で撮影していた話をして食い下がるが、納得できる説明を得られなかった。
そこにイハが来て、町子が助けを求める。
「下手やったからですね」
そのイハが、上映会に来なかった青の店にやって来た。
青は自分のシーンがカットされていたかを尋ねると、イハは映っていたと嘘をつき、笑みを浮かべたあと、青の表情を凝視する。
 |
| 「全部、カットされました?」「いや。出てましたよ」 |
 |
| 「マジで?」 |
その直後、青がアパートに戻ると、雪がいて、二人が別れた日の誕生日ケーキを冷蔵庫から取り出し、まだ食べられるか確かめ、大丈夫だと言って笑い合うのである。
ラストシーンである。
【以上、起承転結がなく、関係交叉の中に「間」があるために、些か長尺になった映画を、テーマに合わせてエピソードを凝縮した次第です】
3 男女関係の濃密度の色とりどりの情態
暑苦しいまでに「怒鳴る映画」と切れ、熱量が低い典型的な「怒鳴らない映画」。
殆ど、唯一無二の映画作家・ジム・ジャームッシュ監督の世界である。
―― 以下、批評。
人間の感情は複合的だが、その中で複雑な表情を見せるのは、男女関係の感情という厄介でありながらも、しばしば内面の鼓動の強弱を露呈させる情景の扱いにくさ。
感情の質の微妙な落差と、関係濃度の密度の差異が、そこに張り付いているからである。
感情の等質・等量感こそが、男女関係の濃密度のマキシマムな様態を表現するということ ―― これに尽きないだろうか。
その辺りが、この映画でほぼ完璧に切り取られていたこと。
それが、男女関係の色とりどりの情態を描いた本作の成功の要因であると思われる。
この映画には、限定エリアで呼吸を繋ぎ、「基本・受け身」で、「弱毒化・非武装化」されているが故に、他者から侵入されやすい脆弱なる主人公・青に絡む4人の女性が登場する。
―― まず、青とイハの関係。
「…僕は雪との馴(な)れ初めから、彼女がどんな人だったか、そして、浮気されたのに振られたことなど、すべてを話した。イハにはなぜか、その話をしてもいいと思えたし、引き摺っていることも素直に話せた」(青のモノローグ)
このモノローグで判然とするのは、知り合ったばかりのイハとの関係が、相手を「特別の異性」として印象付けるものではなく、人に話せないプライバシーを気軽に話し合える存在であったということ。
その意味で、心理的距離感が近接していたと言える。
「何か、こういう距離感のまま、付き合っていくことって、できへんのかなって、いつも思う」
このイハの言葉で分かるように、両者の関係の質の本質が、男と女の友情の成立を充分に窺わせるもの。
「友達になって欲しいかも。友達おらんし、私」
だから、この言葉に結ばれる。
両者の関係の質が変容しないとも言えないが、少なくとも、延々と続くイハとの関係交叉によって、青の鬱々した感情が浄化されていったのは間違いない。
その意味で、青とイハの長回しは、元カレから追い駆けられるストレスを抱え、「友達」を求めるイハにとっても大切な時間となっていた。
「弱毒化・非武装化」されている青の存在価値は、「束縛し、面倒臭い」3人目の元カレと違って、解放感を感受する個性に充ちているから、関係の継続性があるとも言えるが、その場合、イハの方からアプローチすることが条件づけられるだろう。
―― ここで補足したい。
気になるシーンがあったからだ。
イハが映画上映の当日、青を訪ねるシーンである。
その目的は何だったのか。
直截(ちょくさい)に言えば、青のカットが上映されていたという嘘を伝えることで、気にしているだろう上映日に現れなかった青を慰撫(いぶ)すること。
だが、何でそこまでして嘘を伝えようとしたのか。
これには、伏線がある。
後述するように、青のカットが上映されていない理由を些か攻撃的に詰め寄ってきた冬子に対して、「下手やったからですね」とまで言い切ったことを気にかけていた。
その時、冬子という第三者の存在の臭気から、青に対する異性感情を読み取った。
それ故、再映されないという事実を知らない冬子が、青の気持ちを忖度し、上映カットについて話さないとイハは判断したので、その日のうちに青を訪ね、嘘を伝えたのである。
なぜなら、友達であるからだ。
「友達やんかあ」
この一語に収斂されるのではないか。
―― 次に、青と冬子の関係。
「結婚してる人にしか魅かれなくて…」
こんな打ち明け話を正直に告白する冬子にとって、青の存在価値は、青が考えている以上に、求められる特定他者であったとも思われる。
青によって傷つけられた際の、誠意のこもった青の謝罪は、男女関係のあった店長の逝去による孤独を埋めるに足る唯一の話し相手だった。
その話し相手が、店長に代わる「特別の異性」として求められる存在であったか否か、何とも言えないが、冬子と青の感情が等質であったとは思えないから、当然、男女関係の等量感を共有することがない。
だから、同じエリアで呼吸を繋ぐ、古着屋と古書店の店員以上の心理的距離感を保持したまま、二人の関係は延長されていくだろう。
しかし、以上の解釈では、二人の関係の本質に迫れないような思いが、私の中で蟠(わだかま)っている。
諄(くど)いようだが、店長の死の問題である。
店長の死に起因するグリーフ(悲嘆)が、彼女の自我を丸ごと囲繞し、渦巻き、「店長の非在」という日常に耐えられなかった。
グリーフの極みに囚われていたのである。
この視座で、映画を考察する必要がある。
そう考えると、二人の関係の見方が変わってしまうのだ。
何より、そんな冬子が、物語の中で、唯一、主体的に動くシーンがあった。
これが、ずっと気になっている。
なぜ、そこまでして、冬子は動いたのか。
少なくとも、彼女の日常のブル―を浄化するには、ほんの僅かでもグリーフを癒す何かが必要だった。
これ以上、自己肯定感の劣化を被弾すれば、鬱の地獄に搦(から)め捕られてしまう。
目一杯、グリーフを吐き出さねばならなかった。
それには、自らに近接する特定他者を求める。
それが、青だった。
「基本・受け身」で、「弱毒化・非武装化」されているからである。
 |
| 「基本・受け身」だから、オファーを受け、冬子に手伝ってもらって演じても失敗する青 |
ここでも繰り返しになるが、何より重要なのは、青によって傷つけられた冬子が、心優しい青に向かって、グリーフの内実を吐き出し切ったシーンである。
“語る”という行為自体で、相当程度、浄化されるのだ。
だから、青の上映カットについての、過剰な物言いに振れていく。
度を越したとも思えるこの行為もまた、同じ文脈で説明できるだろう。
結局、物語の中の冬子の行為の本質は、グリーフ
ワーク(悲嘆の心的プロセス)であったということに尽きるのではないか。
そう思うのだ。
―― 青と町子の関係について言えば、自明のことだが、映画の出演のために必死で練習してダメ出しされた古着屋と、ダメ出しした美大生の映画監督という関係でしかないから、いつしか忘却の彼方へ消えていくに違いない。
―― そして何より、青と雪の関係。
陋劣(ろうれつ)なる袈裟斬(けさぎ)りで、不活化しないウイルスに侵蝕されたようなブルーのラインから、青と雪の関係が描かれていくが、もう、この伏線は回収し得ないようだった。
「ごめんなさい…間宮君と付き合って、分かったの。前の彼氏が、いかに居心地が良かったかって…そっちの方が私には楽しかったの。もう、遅いけど」
そんな情況に囚われている雪が、自分の思いを決定的に表現する契機を作ってくれたのは、この映画で二度登場する奇態な警官の存在。
唯一、「ザ・スズナリ」(演劇専用の小劇場)の前で、青に吐露した自分の恋バナを雪にも繰り返す、リアリティ欠如の警官の導入は、物語の推進力としてのトリックスターであった。
 |
| 「ザ・スズナリ」の前で |
 |
| 【下北沢】ザ・スズナリ |
姪に対する愛を、3親等であるが故に告白できないで悩む警官は、職質した雪に対して、こんなことを吐露するのである。
「姪っ子がね。俺とあまり歳、変わんないのよ。まあ、色々あって連れ子なの…でも、ぶっちゃけ好きなんだよね。その姪っ子のこと…でもまあ、結ばれることはないじゃんか。でもね。今度、告白しようかなって思ってるんだよね。どうせ、ダメって分かってるんだけどね。やっぱ、言わないと、次、行けないっていうか。どう思う?」
赤の他人に対してプライバシーを全開する警官に感謝し、雪はきっぱりと言い切った。
「ありがとう。私も自分の気持ち、ちゃんと伝えてみる」
「もう、遅いけど」と諦念した雪が、この想いに繋がったのは、著名な俳優と付き合って初めて分かった、青の存在価値の大きさだった。
間宮との付き合いを深めるほど壊されていく、自らが求める〈愛〉の情景。
 |
| 朝ドラ俳優・間宮武 |
間宮の存在の重量感が希釈され、相対化されたことで、蘇生する青との決定的別離への悔い。
「楽しくない」・「気を使う」・「バランスの悪さ」で、ダメになってしまった俳優の彼氏と違って、青の存在は、それとは真逆の唯一無二の異性の輝きを放っていた。
そう思ったのだろうか。
一方、今尚、雪に対する青の想いが延長されていて、壊れていないのだ。
 |
| 雪に対する想いの強さで、部屋に戻っても頭の中は雪のことばかり。この直後、倒れ込んでしまう |
だから、雪の想いを察知するのに鈍すぎる反応を繰り返す、青という男の非武装過多の希少性。
それは、男と女の〈愛〉の等質・等量感がピタリと嵌った時間だった。
その継続力が保証できなくとも、少なくとも、「今」は大丈夫である。
かくて、二人の関係が復元する。
他者との関係の挫折を経由しての復元だから、その情景には澱(よど)みがなく、相当程度、浄化されていた。
―― 観ていて、思わず、笑いを堪えられないシーンがあった。
「会わしてくれて、ありがとう。さようなら」と言い放って、出ていった間宮に声をかけ、雪に対して、青が「これでいいのか」と叫ぶシーンである。
青のこの行動には、「無意識の偏見」(この場合、「人気俳優は女を食い物にする」という偏見)が垣間見える。
だから、雪に「バカ」という一言で片付けられた。
そこに、極め付けの鈍感さが張り付いているが、正真正銘の「バカ」ではないことを知るが故に、雪は「(それでも、或いは、それだから)好き」という、それ以上にない決定言辞を添えたのである。
―― 男と女の関係は、何となく延長されていけば、馴致した物理的共存の強さが、得てして、心理的共存の安寧を支え切ってしまう強さを発現させる。
私たちの〈愛〉の情景は、大抵、こんな様態を垣間見せるのではないか。
(2022年1月)





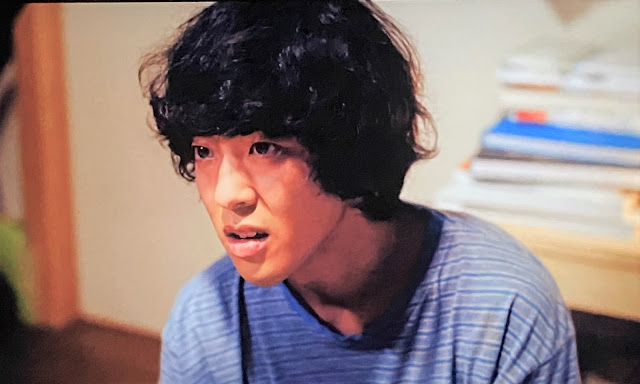































































0 件のコメント:
コメントを投稿