<反復的、且つ、侵入的で、苦患の記憶が想起し続ける冥闇の世界に閉じ込められた男の悲哀が漂動する>
1 「何が起きているのか、さっぱり分からない」と漏らす男の少女救済譚
誘拐された少女を連れ戻すという闇の仕事で生計を立て、老いた母と暮らす男・ジョー。
 |
| ジョーと母 |
そのジョーが、雇い主のマクアリーから仕事を頼まれる。
「なぜ俺を呼んだ?」
「州上院議員、アルバート・ヴォット。昔、俺が彼の親父を警護してたが、その後、縁が切れてた。ヴォット議員の妻は、2年前に自殺。10代の娘は、それ以来、家出したまま。娘と連絡が途絶えたと、ヴォットから電話があった。彼は現知事と選挙活動中で、警察沙汰は避けたい。現金5万ドルの仕事だ」
「手掛かりは?」
「彼に届いた匿名メールにある住所が。午後2時に、彼と会ってくれ」
マクアリーとの会話である。
早速、ジョーはヴォットに会いに行く。
 |
| ヴォット州上院議員 |
「娘さんがいたら、必ず連れ戻します」
「君は残忍だって聞いた」
「時にはね」
それだけだった。
ジョーはヴォットの娘・ニーナの写真をポケットに入れ、次の待ち合わせ場所を指定した。
そして、人身売買の拠点に侵入し、警備員をハンマーで殺し、ニーナを救出する。
車を止め、隣の座席に座るニーナに話しかけると、少女はジョーに抱きついてきた。
「大丈夫、大丈夫だ…そうじゃない。そんなことしなくていい。パパの元へ帰ろう」
二人はモーテルに入り、父親の迎えを待つことにする。
ところが、テレビでヴォットが飛び降り自殺をしたというニュースが流れるのだ。
肝心の依頼主の死に驚愕する間もなく、モーテルの警備員が警官2人を連れ、ドアを開けた。
その途端、警備員は背後の警官に射殺され、一人はニーナを連れ去り、もう一人はジョーと格闘して殺された。
射殺された警備員の血飛沫(ちしぶき)を浴びるジョー
「何が起きているのか、さっぱり分からない」
常に、この言葉がジョーを襲ってくるようだ。
いつもの自傷行為で、歯を紐で抜き、血を滴らせるジョー。
児童期に家庭内暴力が常態化していて、児童虐待のトラウマを抱える彼には自殺願望がある。
そのジョーはマクリアリーに電話をかけるが、留守録のテープが流れるのみ。
事務所へ向かうと、マクリアリーは既に殺されていた。
そればかりではない。
雑貨屋の店主で仕事の仲介者でもあった、エンジェル父子も殺されたのである。
混乱の中、子供の頃に受けた父親の虐待のフラッシュバックに苛まれ続けるジョー。
「背筋を伸ばして、まっすぐに」
そんな言葉が繰り返し、侵入的想起するのだ。
不安を抱えて帰宅するや、ジョーは凍り付く。
今度は、母親がベッドで銃殺されていたのである。
階下に人の気配がしたので、降りて銃を放つと、一人は死に、一人は絶命せずに倒れていた。
気息奄奄(きそくえんえん)の男が、ニーナの居場所がウィリアムズ州知事のところであると吐く。
この男が黒幕だったのだ。
「母は怖がったか?」
「眠ってた」
ラジオからかかる「I've Never Been to Me」(愛はかげろうのように)に合わせ、息絶え絶えの男が口ずさむ。
ジョーも一緒に歌い、死にゆく男の手を握る。
母親の遺体をビニール袋に包んで車に乗せ、美しい森の湖畔へ行き、自らも石をポケットに詰め、潜って母を水葬した。
 |
水葬された母
水中に深く沈むジョーは、フラッシュバックで再現されるカウントダウンに入り、自死する行為に振れるが、石を捨て、湖から生還する。
ニーナの救済を果たしていないのだ。
ニーナを救うべく、ジョーはウィリアムズの選挙事務所に向かい、組織の男たちの車を追尾し、豪邸に入り込む。
警備員らをハンマーで撲殺し、ニーナの部屋に辿り着くと、ウィリアムズは既に喉を掻き切られて死んでいた。
嗚咽するジョー。
ここでも、フラッシュバックが彼を襲う。
階下のダイニングルームに行くと、ニーナが血だらけの手で食事をしていた。
傍らには、血の付いたカミソリが置かれていた。
ニーナがウィリアムズを殺したのである。
ニーナに近寄り、少女の腕に手を添えるジョー。
「大丈夫よ、ジョー。心配しないで」
2人は邸を出て、レストランに入った。
「どこへ行くの?」
「そうだな。どこでもいいぞ。どこへ行きたい?」
「分からない」
「俺も分からない」
ジョーの言葉を聞くや、ニーナは席を立ち、トイレに向かった。
為すすべのないジョーは、一筋の涙を零し、銃で自らの喉を撃ち抜く。
ニーナが席に戻り、ジョーの頭に手を置く。
「ジョー、目を覚まして」
ジョーの自殺は夢だった。
「何?」
「行きましょ。今日は、いい天気よ」
「確かに、いい天気だ」
二人が座っていた椅子が映し出され、「何が起きているのか、さっぱり分からない」と漏らす男の少女救済譚の物語が、まるで何もなかったかのような印象を観る者に与えて、ラストカットとして閉じていく。
2 反復的、且つ、侵入的で、苦患の記憶が想起し続ける冥闇の世界に閉じ込められた男の悲哀が漂動する
「彼が少女たちを救うのは、お金のためでもないし、仕事が楽しいからでもない。過去のトラウマに縛られ、それに左右されているからだ。彼は幼い頃、自分の弱さを痛感した。母親も自分も守れなかったからね。その埋め合わせとして、彼は少女たちを助けてるんだ。(略)具体的虐待を受けた人には、ある種の発達遅延が見られる。ジョーにも、まるで子供のような面がある。母親との関係で、これを表現したかったんだ。(略)ある意味、昔の関係性のまま止まってるんだ。楽しくもあり悲しくもある。この関係がずっと続いている。(略)母親の世界は、その時代で止まってる」(「ホアキン・フェニックスが明かす異色の主人公のキャラ作り/映画『ビューティフル・デイ』インタビュー」/YouTubeより)
 |
| ホアキン・フェニックス |
ホアキン・フェニックスのこのブリーフィングが、刺々しい映画のエッセンスになっている。
【以下、提示された映像の情報の範疇で批評したい。広告画像はOKだが、できる限り映像から拾っていきたいと考えている】
ホアキン・フェニックスが言う「過去のトラウマ」には二つある。
一つは、従軍時代に、戦地でお菓子を与えた少女が、それを奪う少年に銃で撃たれて死んだ一件。
【もう一件、少女たちが倉庫のようなスポットに閉じ込められている映像もあるが、背景が全く不分明なので、批評から除く。反省含みで書けば、原作を準拠枠にした批評は適切ではないと考えているので、原作ベースの批評は私の中ではOUTである】
もう一つは、父親による家庭内暴力を母子共に被弾したこと。
前者は、誘拐された少女を連れ戻すという現在の闇の稼業に繋がっていることで、相応に昇華されている。
何より問題なのは、後者である。
自らも父親の暴力を被弾したばかりか、母親がDVの犠牲になっている時、クローゼットに隠れ、カウントダウンしながら母親の悲鳴を聞き流し、この恐怖の時間の中で、逃げ続けた自分の弱さへの悔い。
 |
| 虐待される母 |
 |
| クローゼットに隠れるジョー少年 |
これがジョーの生涯に重くのしかかり、過大なストレスの負荷を負っている。
「まっすぐ立て。猫背は女々しいぞ。15・14…7・6・5・4・3・2・1…もっと頑張れ…言え…もっと頑張ります」
 |
| フラッシュバック・父を怖れるジョー少年 |
ビニール袋の中で藻掻(もが)くフラッシュバックを提示した、自傷行為とも言えるオープニングシーンは鮮烈だった。
罵詈雑言(ばりぞうごん)を浴びつつ、カウントダウンすることで恐怖の時間が過ぎ去ることを待ち、耐えていくビニール袋のシーンが繰り返され、後半生に至っても、ジョーの人生には、「機能不全家庭」で育った者の自我形成の「発達遅延」が浮き彫りになっていた。
立場が脆弱な被虐待児は、親の心身両面に及ぶ暴力に屈服し、自己憎悪と劣等感に充ちた自我を形成し、これがジョーの自傷行為のうちに発現されるのだ。
ここで、児童虐待の克服課題の艱難(かんなん)さについて想起せざるを得ない。
「トラウマ」・「愛情」・「尊厳」の3点である。
ジョーの場合、後半生に至っても延長されている家庭内暴力の「トラウマ」が、ビニール袋を被るシーンを通して繰り返されていて、その根の深さは、自死に振れるリスクを高めていくばかりであった。
辛うじて、彼の〈生〉を繋いだのは、「ニーナ救済」という役割を負っているからであり、被虐待の心的外傷の「埋め合わせ」が自己完結していないからである。
「愛情」については、年老いた母親との関係の中で充填してきたが、しかし、ジョーと母親の関係は「共依存」と言っていい。
自我が未成熟なジョーは、母親に対する「イネイブラー」(依存症者に過剰な援助をする者)の存在と化していたのである。
そんなジョーにとって、母親の死は自らが招いた行動の結果であるが故に、その「共依存」の対象の喪失が自死に振れる決定的な事態を惹起せざるを得なかった。
しかし、ジョーが自死に行き着く情態を開くことがなかった。
「ニーナ救済」という役割を捨てることができなかったからである。
 |
| ニーナの父・ヴォット(右) |
「ニーナ救済」は、一定程度の「自己救済」の意味を内包していた。
「ニーナ救済」なしに「時間」を繋げないのだ。
ところが、ジョーの「ニーナ救済」もまた、外形的には頓挫する。
救済されるべきニーナこそ、「自己救済」を有形化していたのである。
寧ろ、ジョーの「ニーナ救済」は、ニーナの「ジョー救済」を可視化する。
救済されたジョーは、ここでも惑乱する。
なぜなら、「尊厳」の獲得というジョーの枢要なテーマが等閑(なおざり)にされているのだ。
だから、可視化されたニーナの「ジョー救済」が、「明日」を迎えるジョーの「尊厳」の復元・把持の保証にはならないのである。
「自分はここに生きていて、この〈生〉を受け入れ、自足する」
この「尊厳」の獲得がリアリティを持ち得ないのである。
ジョーの悲哀だけが生き残されてしまった。
思うに、「尊厳」の獲得を手に入れられないジョーの悲哀の淵源に横たわっているのは、「恐怖」の対象であった父親への「同化」だった。
この心理的メカニズムのコアは、「恐怖払拭」を隠し込んだ無意識的な「防衛機制」である。
男は「恐怖」の対象であった父親に「同化」することで、「強い男」に化けようとする。
そのために、マッチョな身体を作り上げ、自己改造を果たす。
そのマッチョな身体を武器に、男は「行方不明の少女の捜索」という闇の稼業で生計を立てていく。
少女売春宿を「絶対悪」にして、「強い男」をフル稼働させていくのだ。
「絶対悪」に破壊的暴力を振るうハンマーこそ、「非虐待の絶対記号」だった。
「非虐待の絶対記号」としてのハンマーの駆使 ―― これは精神分析学の重要な概念としての「取り込み」である。
父親に「同化」し、自己改造を果たした男にとって、「非虐待の絶対記号」を「絶対悪」への破壊的暴力を「取り込み」、アイテムにすることで「同化」を自己完結させる。
しかし、「同化」を自己完結させる男の防衛戦略は、いつでも破綻する。
「強い男」をフル稼働させていく心理的行程で、一片の充足感をも手に入れられず、フラッシュバックが出来し、突沸(とっぷつ)するばかりだった。
自己嫌悪と自傷行為の連鎖。
ここまでいくと、「適応戦略」それ自体の破綻であると言っていい。
果たして、男に何ができるのか。
「何が起きているのか、さっぱり分からない」
渾沌と迷妄。
児童虐待の克服課題の艱難さ。
それが観る者の視界に這い入ってくるのだ。
「尊厳」の獲得というテーマの深刻さだけが晒される。
それは、再体験症状が発現し、自律神経システムを崩壊させるPTSDの壮絶な破壊力の風景である。
「自分はここに生きていて、この〈生〉を受け入れ、自足する」
ジョーにとって、あまりに希薄な理念系のフレーズだった。
感覚情報・記憶情報の統合の中枢・「眼窩前頭皮質」(がんかぜんとうひしつ)の萎縮が出来することで、反復的、且つ、侵入的で、苦患(くげん)の記憶が想起し続けるPTSDの冥闇(めいあん)の世界に閉じ込められても、認知行動療法による治療を拒否するに違いない男の未来に待つのは、それ以外に入り込めない自死という「絶対緩和」への簡便な越境であるだろう。
 |
 |
そう、思わざるを得なかった。
―― 最後に、リン・ラムジー監督のインタビューの一部を掲載しておく。
 |
| リン・ラムジー監督 |
「この映画の最後で、ジョーはある意味で壊れてしまう。彼は少女を救うことができず、自分自身を救うことさえほとんどできない。そして世界は不確実で、ただしずっと静かな場所になっている。この映画を撮影していて、ホアキンと私は何度も同じ感情に捉えられたわ。目の前ではあまりにも暴力的な場面が展開していて、私たちはその余波のようなものを受けていた。だから、この映画は心に関わる問題を描いているわ」(『ビューティフル・デイ』:リン・ラムジー監督 インタビュー)
(2021年2月)
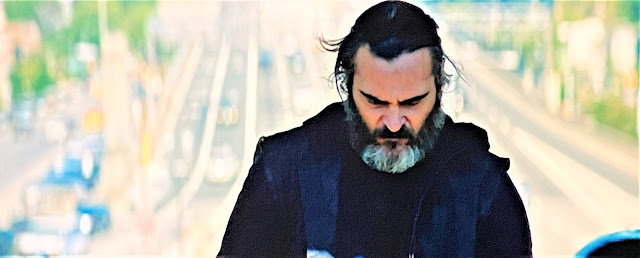







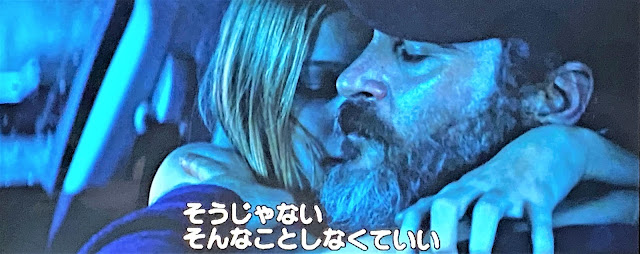

















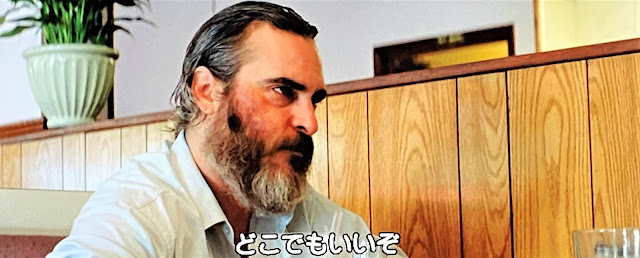

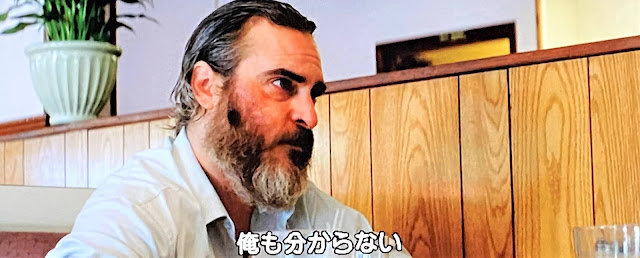




























0 件のコメント:
コメントを投稿