
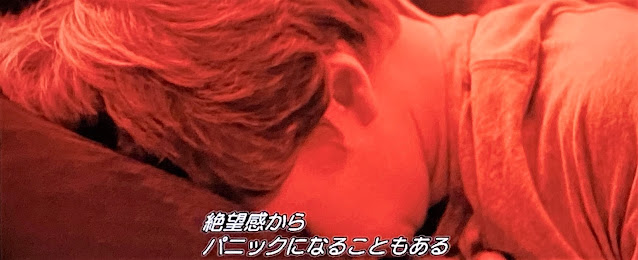




1 「感情に訴える何かが起こると、雷に打たれたように体が動かなくなる。でも跳びはねれば、縛られた縄を振りほどくことができる」
「およそ10年前、10代だった東田直樹は、その著作で知らざれる世界を明らかにした。“自閉症の僕が跳びはねる理由”は、会話のできない自閉症の少年の成長を描いている」(キャプション)
「小さい頃は、自分に障害があると知らなかった。なぜ気づいたか?“普通と違う”みんなが言ったからだ。“これは困る”と。確かに“普通”になるのは、僕には難しかった。今でも人との会話はできない。みんなから見れば、自閉症の世界は謎だらけに違いない。心の中を僕なりに説明することで、自閉症の子供を見守る皆さんの助けになればと思う」(モノローグ)
「言いたいことが言えない生活を、想像できますか?」(モノローグ)
ここから、世界中の自閉症の子供たちが紹介される。
「みんながしないことをするたびに、不思議に思われる。見かけで判断しないでほしい。少しだけ、僕の言葉に耳を傾けて。僕らの世界を旅してほしい」(モノローグ)
インド ノイダ地区
“アムリット”
「娘は、皆と違う物事に反応する。あれは、うれしい驚きだった。アムリットは長年心の中に怒りを抱えながら、それを表現できずにいた。学校で、いじめにも遭っていたと思う。友達が欲しくても、他の子は娘を持て余す。よく何時間も叫んでは泣いていた。私も助けられずに泣いたわ。当時はよく、クレヨンを1箇所に塗りたくっていた。紙が破れて、机に跡がつくほど強く。そうやって懸命にメッセージを伝えていたのでしょう。私は気づいた。これは単なるアートではなく、日常を伝える手段なんだと。どんな物を食べたかも描いてたわ。学校の生徒たちや、見た風景も…これが旅の始まりだった」(アムリットの母)

 |
| アムリット |
「僕は世界をどう見ているのか。見えるものは、みんなと同じでも、それをどう受け取るかが違う。みんなは物を見る時、まず全体を見てから、部分を見ている思う。僕の場合は、まず部分が飛び込んでくる。その後、視界が広がって全体が分かるんだ。僕の目は線や面などにとらわれる。状況を理解するには、記憶の中から最も似た場面を探す必要がある」(モノローグ)

「世界は混沌とした場所だ。脳内で何とか整理しないといけない。自閉症者は、やっとの思いで対処している。そう理解した。東田直樹が、この本を書いたのは13歳の時。僕の息子と同じ自閉症だ。直樹は、いわば心の地図を描いて見せた。たとえば彼が、“雨が降っている”と理解するまでの描写がある。自閉症でない人間には、想像も及ばない独自の音を聴くと、彼は頭の中のカードをめくり、記憶を頼りに“雨”という語に結びつける。かなりの手間だ。直樹が描くのは未知の世界。彼がさらされ続けている混沌とした世界だ。感情が抑えられず、突如パニックが襲う…」(デイヴィッド・ミッチェル “自閉症の僕が跳びはねる理由”翻訳者)
 |
| 東田直樹 |
「娘には、“こだわり”が多かった。私は世間体を気にして、やめさせようとしたわ。でも直樹の本を読んで知った。娘の苦労をね…正しい母親であろうとするあまり、我が子を見てなかった。あの子らしさを抑圧してた」(アムリットの母)
笑顔で抱き合う母娘。
「物は、すべて美しさを持っている。鮮やかな色や印象的な形を見ると、そこだけに心が奪われる。何も考えられなくなるんだ…」(モノローグ)

「ある種の物音や光景が、娘に苦痛を与えたり、喜びをもたらしたりする。アムリットは家に帰ると、まず紙を手に取る。自分の思いを世界に伝えるために」(アムリットの母)
アムリットの描いた大量の絵が運ばれ、会場に展示される。
「話せないことは、気持ちを伝えられないことだ。人として生きるには、自分の意思を伝えることが何より大切だ」(モノローグ)
 |
| アムリットの絵 |
イギリス ブロードステアーズ
“ジョス”
「人と話そうとすると、僕の言葉は消えてしまう。口から出る言葉は本心とは違う…いわば反射的だ。その時、見た物や思い出したことに反射している。言葉の洪水に溺れながら…でも、いつも使っている言葉なら話せる」(モノローグ)
 |
| ジョス |
「ジョスは、すべてを見て、聞いている。幼い頃は、感覚の世界を楽しんでいた。特に光と水に関わるものをね。できるかぎり触れさせた」(ジョスの母)

「10秒だけでも、息子になって世界を感じたい」(ジョスの父)
3.4歳の頃、住んでいた家でのことを具体的に話すジョス。
「彼にとっては、30分前の出来事と変わらない。2歳の誕生日の直前のことも話す。まるで制御不能のスライドショーだ」(ジョスの父)
「時間は、ずっと続き区切りがない。だから戸惑ってしまう。今言われたことも、ずっと前に聞いたことも、僕の頭の中では、あまり変わらない。みんなの記憶は、たぶん線のように続いてる。でも僕の記憶は、点の集まり。その全部がバラバラでつながらない…困るのは、古い記憶が、時に生々しく、頭の中で再現されることだ。その時の気持ちもよみがえってくる。突然の嵐のように…次の一瞬、自分が何をしているか、それがいつも不安なんだ」(モノローグ)


「思春期になり、彼は感覚の世界を楽しめなくなった。不安が大きくなったの」(ジョスの母)
「何かをしたくても、どうしても、できない時もある。体が別人のもののように感じる。壊れたロボットを操縦しているようだ」(モノローグ)
突然、大声で叫び、暴れて父を苦しめるジョス。
「絶望感からパニックになることもある。何か失敗すると、その事実が津波のように押し寄せ、逃げようと必死でもがく。気づけば、残っているのは僕が暴れた跡だけ。自己嫌悪に陥る」(モノローグ)
攻撃的な行動が増え、大変な時期が数か月続き、ジョスは学校を退学になり、自閉症の子供が入れる全寮制学校に転校する。
「今も頻繁に帰ってくるけど、本当に、つらい決断だった」(ジョスの母)
ジョスが楽しそうにトランポリンを跳びはねる。
「僕が跳びはねる理由?僕の体は、悲しいことやうれしいことに反応する。感情に訴える何かが起こると、雷に打たれたように体が動かなくなる。でも跳びはねれば、縛られた縄を振りほどくことができる。気持ちは空に向かっていく。そのまま鳥になって、遠くへ飛んで行けたら…」(モノローグ)
「直樹の著作は、自閉症者への偏見を覆した。“感情がない”だとか、“創造的な知性を持たない”などだ。もしそうなら、本など書けるはずがない。文章を書く自閉症者は板挟みになちがちだ。多くは書いたことを疑われる。あるいは、信じてもらえても、ごく軽度の自閉症だと思われてしまうんだ」(デイヴィッド)
2 「一番つらいのは、自分のことで悲しむ人がいることだ。どうか、僕と一緒に闘ってほしい」
アメリカ バージニア州 アーリントン
“ベンとエマ”
二人はアイスホッケーの選手である。
「話せないと理解力を疑われる。“認知能力に難がある”とね。ベンは今、23歳…言語療法に期待してたけど、結局、16歳になる頃、合わないと分かったの。するとエリザベスが“他の方法がある”と」(ベンの母)
「文字盤を使う子たちを見て、これだと思った。自閉症者の多くは、意識を体に伝えるのが苦手。運動技能の観点から考えても納得がいく。より微細な動きが必要な発話よりも、腕の動きで言葉を伝えるほうが負担が軽い」(エリザベス・フォスラー言語療法士)
「…彼らには文をつづる能力も、知性もある。これまでの“常識”を覆す事実よ」(エリザベス)
 |
| エリザベスとベン(右) |
 |
| エマ(右) |
「“仲間に出会った今、私には、すべてがある”」とエマが綴る。
「僕が口にする言葉は、本心と同じじゃない。声を出せることと、話せることは違う」(モノローグ)
ベンとエマが雑木林の公園を歩く。
音楽を聴きながら歩くエマ。
「“ベンは、よく私に耐えてくれてる。私は、すごく騒がしいのに…彼は私にとって、初めてできた友達”」(エマ)

「“僕らの友情が求めるものは1つ。この世界における安らぎ”」(ベン)。
「みんなは、すごいスピードで話す。頭で考えた言葉が口から出るまでが、ほんの一瞬だ。不思議でたまらない。僕には、知らない外国語で会話するような毎日なのに」(モノローグ)
「“僕らが育んできた友情の意味は、言葉では説明できないものだ。エマは僕の北極星。彼女は超クールだ”」(ベン)
エマの母が二人の宿題を指導していると、しばらくしてエマが激しく拒絶する。
それについて意見を求められたベンは、「“人権の否定”」と答える。
「話せない僕は、よく生まれた理由を考えた。自閉症の人には自由がない。居場所が必要だ。僕らが生きていく世界は、ここだけだ」(モノローグ)
シエラオネ フリータウン
“ジャスティナ”
浜辺で海と戯れる少女。
 |
| ジャスティナ |
「ジャスティナは、僕を真の父親にした。この子がくれた愛は、我々の人生観も変えた」(ジャスティナの父)
「こだわっていることをやると、少しだけ落ち着く。繰り返しは心地いい。不確実さから自分を守ってくれる」(モノローグ)
「自閉症の子は、多くの文化で“恥”とされる。子育て中、感じたのは、愛情や共感よりも嫌悪や蔑みの目だった。ある日、この門の外で、娘はパニックになり、叫びながら大暴れした。人々の表情が語ってたわ。“この子は悪魔に取りつかれてるんだ”と…他の親にも会ってみたかった。街では自閉症の子を見ない。それでグループに参加した。でも自閉症を恥とする根強い文化のせいで、集まる家族は限られていた。自閉症に対する数世紀にわたる偏見は、今も世界中で続いてる」(ジャスティナの母)
グループで発言する母親たちは、皆、近所で悪魔扱いされ、差別されていると訴える。
ジャスティナが、突然外に出て、それを追う母親。
ジャスティナは泣いている。
「みんなは、たぶん自然を見て、木や草花の美しさに感動する。僕の場合は違う。人からどれだけ否定されても、自然は僕を抱き締めてくれる。自然を見ていると、この世界に生きていてよいのだと思える」(モノローグ)
「ここの人々は、老後は子供に面倒を見てもらうものと考えてる。だから、自閉症の子は何も与えてくれないと見なす。共同体からの圧力に耐えかね、我が子を置き去りにする親も多い」(ジャスティナの父)
「娘のような子は、生きていくのも大変」(ジャスティナの母)
「自閉症は長年、悪霊や呪いのせいとされた。20世紀前半には、“知恵の遅れ”だと、不当に虐げられてきたんだ。我が子に重ねると、つらい…自閉症者は差別されてきた。自閉症でない人間が理解しなかったせいでね」(デイヴィッド)
「僕らはきっと、文明の支配の外に生まれた。多くの命を殺し、地球を壊してきた人類に、大切な何かを思い出してもらうために」(モノローグ)
「現実を知ったからには、行動を起こすべきだ。我々は思い切って、テレビやラジオに出演した。自閉症を広く知ってもらうためだ。当事者が堂々と、表を歩けるようにしたかった。皆と同じように。2017年には、学校が設立した」(ジャスティナの父)
「子供たちも、その家族も、大きく変わった。こういう学校は全国初。何か月もかけて、近隣住民を味方につけた。皆、古い考えにとらわれて、最初は警戒してたわ。でも今では、生徒たちの名前も覚えてくれた。会えば挨拶もしてくれる。いい関係ができたことで、子供たちの安全も高まった。新政府も当校を認可し、人々の意識は変わりつつある」(ジャスティナの母)


教室の授業の様子。
「多くのことを学んで成長したい。同じ願いを持つ自閉症者は大勢いる。僕らだって成長したい…一番つらいのは、自分のことで悲しむ人がいることだ。どうか、僕と一緒に闘ってほしい」(モノローグ)
一緒に色彩のテントの中を走るジョスと父親。

「彼との時間は“今”そのもの。一緒にいると、過去の悔いや現在の悩み事から、自由になれる感じがする」(ジョスの父)
「未来の世界は誰にも分からない。願わくは、ジョスを受け入れ、理解を示す場であってほしい。我々がいなくなっても、大丈夫なようにね。親としては、それが…だから未来の話は苦手だ。あの子が1人になると思うと怖い」(ジョスの父)
アムリットの“街角のすばらしき人々”という個展が開催される。
作品を見入る来場者たち。
「“僕らは変えられる。自閉症をめぐる対話を”」(ベン)
「“僕らが対話に加われば、対話は変えられる”」と文字盤を使って、エリザベスが答えを引き出す。
少年が翻訳者を窓の外から覗き、ガラスに息を吹きかけ去る。
外の気配に気づいたデイヴィッドが窓の外を見る。
ラストカットである。
3 自分たちのリズムを壊すことなく、成長を望む思いを共有していく
4か国の自閉症者の内的世界を紹介しながら、日本人の「僕」の「心の地図」を描く映画。
 |
| 「僕」 |
これが本篇の骨子である。
世界を理解するには脳内で整理しなければならない。
たとえば “雨が降っている”と理解する時、「定型発達」(普通)の人は、頭の中のカードを捲(めく)り、記憶を頼りに“雨”という語に結びつけるが、自閉症の場合、曝され続けている混沌とした世界でしかない。
この未知の世界に呑み込まれ、感情が抑えられず、突如パニックが襲ってしまうのだ。
「人として生きるには、自分の意思を伝えることが何より大切だ」と理解できるが、「口から出る言葉は、本心とは違」ってしまう。
だから、「言葉の洪水」に溺れながら、「見た物や思い出したことに反射」するだけ。
全体を見てから部分を見ている「定型発達」の人と異なり、自閉症の場合は部分が飛び込んできた後、視界が広がって全体が分かるのだ。
記憶が「線」である前者と異なり、後者は「点」の集合だから、バラバラでつながらないから苦労する。
最も厄介なのは、「古い記憶が、時々生々しく、頭の中で再現されること」。
まるで、その古い記憶がが「嵐」のように襲ってきて、「自分が何をしているか」分からないという不安の只中で日常性を繋いでいる。
この不安が爆発することがある。
「何か失敗すると、その事実が津波のように押し寄せ、逃げようと必死でもがく」。
この「絶望感」がパニックを起こす。
これが、自閉症のパニックの構造である。
「悲しいことや、うれしいことに反応する。感情に訴える何かが起こると、雷に打たれたように、体が動かなくなる」。
これを克服するために「跳びはねる」。
跳びはねれば、「空に向かっていく」気持ちになれからだ。
コミュニケーションの手立ては、文字盤を使うことから開かれた。
「より微細な動きが必要な発話よりも、腕の動きで言葉を伝えるほうが負担が軽い」ので、文字盤は相互理解の最強のアイテムとなった。
「定型発達」の人は、「頭で考えた言葉が口から出るまで」の話すスピードが高速なので、自閉症者には文字盤が最も都合がいい。
これが、自分たちの相互理解の格好のリズムを作ってくれるのである。
何かあるものへの自閉症者の拘りの強さは、繰り返しの心地良さによって「自分を守ってくれる」からだ。
「文明の支配の外に生まれた」自閉症者の存在には意味があると信じたい。
だから、自分たちのリズムを壊すことなく、成長を望む思いを共有する自閉症者は、現実の辛さに負けずに闘っていかねばならない。
「みんなのように生きられたら、いいのに思っていた。でも今は、自閉症が治るとしても、このままの自分を選ぶ」
僕には自閉症が“普通”だから。
「みんなの“普通”が分からない」この「僕」のモノローグの中に、映画のメッセージがある。
「僕は小さい頃、心配でたまらなかった。自分はどうなるのか。人として、満足に生きられるのか。すべての自閉症者を代表することはできないが、みんなに理解してほしくて、この本を書いた。僕の未来が、みんなの未来とつながること。それが僕の望みだ」

かくて、このモノローグに結ばれたのである。
以上、要約すれば、こういうことだろう。
―― 親の熱心なサポートのお蔭で、成功例のみを上手に切り取った、極めてポジティブな映画である。





自閉症者に対してと言うよりも、自閉症に対する「定型発達」の人の無理解・誤解を解くために製作された映画という印象が強く、「これが私たち自閉症の世界である」ことを、基本的にドラマとの境界が曖昧なドキュメンタリーという形式で訴える、一種のマニフェストと受け止められる。
 |
| ジャスティナと父 |
それは同時に、自閉症の子を持つ親御さんへの励みとなるので世界中で読まれ、観られているのだろう。
だから、「僕」という一人称で表現された映像にはパワーが漲(みなぎ)っていた。

このパワーこそ、無知に起因する偏見・差別に晒されている世界中の自閉症者と、それを見守る家族との連帯を呼びかける熱量の束そのものとなっていて、そのアート性ともリンクして訴求力を高めていた。
 |
| ジャスティナと父 |



 |
| 【文字盤ポインティング」を使用する原作者・東田直樹/13歳のときに書いた著作『自閉症の僕が跳びはねる理由』(2007年出版)が、2013年夏、英国のベストセラー作家デイヴィッド・ミッチェルとケイコ・ヨシダよって英訳され、その後、22カ国で翻訳された(ウィキ)】 |
多くの人々に観られるべき映画である。
4 自閉症は脳の先天的な発達障害である
【以下、人生論的映画評論・続「梅切らぬバカ」('21) からの批評を補筆・引用した拙稿です/以下、画像】
自閉症は、高機能自閉症、アスペルガー症候群と共に、「自閉スペクトラム症」と呼称される脳の先天的な発達障害である。(スペクトラムとは「集合体」という意味)
 |
| 自閉スペクトラム症 |
【2013年の「DSM-5」(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)で「自閉スペクトラム症」と明記】
【自閉症の知的障害の有無などの境界を定めることが難しいので、「曖昧な境界の連続性」という意味において、「スペクトラム」という用語が定着している】
普遍的ではないが、精神遅滞の頻度は相当程度高い。
まず、この把握が前提になる。
然るに、相当に幅広い個人差を有している現実も無視できない。
何より不幸なのは、脳の発達異常であることによって、根本的治癒が不可能であるという冷厳な現実を無視したら、今もなお数多いる、「自閉症者は天才を生む」という、真に不幸なる「負のラベリング」から、いつまでも解放されず、近年、話題になることが多い「アスペルガー症候群」(「自閉スペクトラム症」)に対するロジカルエラー(論理的過誤)を犯すことになる。
脳の仕組みが健常児(「定型発達児」)とは明瞭に異なっている事実誤認が容易に修正されず、例えば、「アスペルガー症候群のボーダーライン」と言われるマーク・ザッカーバーグ(敬称略)のように、些か言語コミュニケーションを苦手にしているように思われながらも、ハーバード大学のコンピューターを簡単にハッキングすることで、学内の女子の顔の格付けサイトを立ち上げる発想を具現する能力から開かれたプログラミング能力によって、「激情的な習得欲求」⇒「一点集中力的な『創造力』の開発欲求」という稀有な能力に変換させていく振れ方は、殆ど「天才」の範疇であると言っていい。
 |
| マーク・ザッカーバーグ |
未だに、知的障害を伴わない「高機能自閉症」としての「アスペルガー症候群」という把握が研究者間で共有されていないにも拘らず、「自閉症」=「アスペルガー症候群」=「天才」という愚昧な感覚で氾濫する現実は、アルゴリズムを蹴飛ばし、簡便な判断によって直感的に判断を下す「ヒューリスティック処理」の陥穽に流れやすいから厄介なのである。
加えて、「サリーとアンのテスト」(自閉症者は人の心を理解できないことを示すテスト) で有名な「心の理論」(相手の心中を推察する能力)が、ミラーニューロン(他者の喜怒哀楽を理解する能力)との関連で語られることが多いが、それもまた、どこまでも発展途上の仮説の範疇を突き抜けられていないばかりか、「心の理論」に関わる研究自体が、その概念の包括力において困難な、自閉症の様々な行為を科学的に説明し得ない現実がある。
 |
| 【4歳未満の子供の多くは「案の箱を探す」と答えます。4歳以上の子どもになると「サリーのカゴを探す」と答える割合が高くなります。それだけ自分と相手を別々に考えたり、逆に重ね合わせたりすることが子どもにとって難しいってことです。「サリーとアン課題」という有名なテストです】 |
然るに、特定の分野に限ってのみ信じ難い能力を発揮する、原因不明の「サヴァン症候群」を「自閉スペクトラム症」(ASD)の範疇に入れるとしても、式場隆三郎(国府台病院を創設した精神科医)によって「発見」され、注目された、我が国の山下清(記憶を基に完璧な貼絵アートに再現)の例を含めて、その出現率は稀有であるが故に、決して通常の自閉症者を代表する者ではないということである。
 |
| 山下清(ウィキ) |
だから、「広汎性発達障害」(「自閉スペクトラム症」)と括られるケースが多いように、「アスペルガー症候群」や「サヴァン症候群」と必ずしも地続きになり得ない、知的障害を伴い、IQが70以下であるが故に「低機能自閉症」とも呼ばれている「カナー症候群」は、学習障害を併発する確率が高く、その出現率も少なくない。
同様に、先述したように、出現率が比較的に高い「アスペルガー症候群」と自閉症障害者の関連も特定できない現実を無視できないのである。
私塾時代に、私自身が経験した「広汎性発達障害」の児童は、「カナー症候群」の範疇に入ると思われるケースだったので、学習障害の併発によって、常に苛立っているところがあり、「反響言語」(相手の発言をリピートする)、「フラッピング」(手を羽ばたかせるような仕草)や、特定の対象に対して強い興味を示す「同一性の保持」という自閉症特有の症状があり、視線を合わせないこと、接触を極度に嫌う傾向が顕著で、更にアプローチを間違えると、突然パニックが起こる現象に対して、正直、緊張の連続だったと回顧している次第である。
 |
| 自閉スペクトラム症の診断基準 |
 |
| 自閉スペクトラム症の診断基準 |
言語コミュニケーション、対人関係、行動傾向、集中力、感覚(過敏)、想像力、柔軟性、運動・学習能力、感情的知性(感情察知能力)などに障害が見られるが、但し「自閉スペクトラム症」に括られながらも、知的障害を伴わない「アスペルガー症候群」と峻別する必要がある。
それ故、「自閉スペクトラム症」に罹患する対象人格の特性を理解した上で、個々に合った「環境調整」のもとで適切なアウトリーチが求められるということ。
「特性」と「環境」の融合 ―― これに尽きるだろう。
そんな折、多様性社会の実現を目指し、華やかなドレスを着た車椅子障害者を先頭に、健常者と共に障害に関係なく練り歩く、140人の「インクルーシブパレード2022」(5月27日)が墨田区の錦糸公園周辺で開かれた。
 |
| 「インクルーシブパレード2022」 |
誰も仲間外れにしない「社会的包摂」の広がりこそ、我が国の喫緊のテーマなのだ。
(2022年11月)















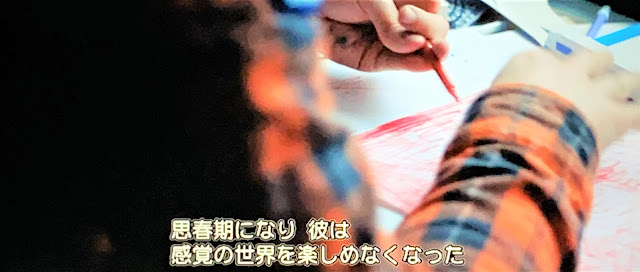































.JPG)











0 件のコメント:
コメントを投稿