



1 「あんたは、俺の言葉の本当の意味を理解できる人間だ」
一人の女が、精神科のカウンセリングで『青髭』という本を音読するが、結末を知っていると言って、途中で止めてしまう。
ホテルで娼婦が左右頸動脈を切断され、胸にかけてⅩ字に斬られ失血死するという猟奇殺人が起きた。
犯人は、服や財布をそのままにして逃走したが、程なくして捜索に入った警視庁の高部(たかべ)がホテル内で発見する。
高部の友人である精神科医の佐久間が犯人の尋問の録画を見たが、これまでのケースと同じで「異常なし」と言う。
 |
| 高部(右)と佐久間 |
この2カ月で3件、首をⅩ字に切り裂かれる手口の殺人事件が起きており、担当の高部は頭を悩ましている。
マスコミにも手口は公表しておらず、テレビや小説の影響もなく、それぞれの犯人は接点もなく、頭が異常なわけでもない。
「じゃあ、偶然だな。犯罪はいつも、特別な意味があるように見える」と佐久間。
「偶然で、こんな手の込んだことができるのか?」
九十九里浜の中心部にある千葉の白里海岸。
海辺の砂浜で腰を下ろして添削作業をしていた花岡は、空を見上げていた若者と目が合い、近づいてきたその男に声をかけられた。
「ここはどこだろう?」
「白里海岸です」
その男は少し歩いて戻り、またどこかを訊ね、帰ろうとする花岡に、自分が誰かも分からないと訴え、膝から崩れ落ちる。
「助けてよ。頼むよ。俺、何にも思い出せないんだ」
自宅に連れて帰った花岡は、コートに付けられたクリーニングのタグから、男の名前が間宮(まみや)であると特定する。
花岡が間宮の家族や仕事について話を聞くと、「あんたから先に話して」と言うので、小学校の教師で、家族は妻が一人だと答える。
今度は間宮に、「どうしてあの海岸にいたんです?」と訊くと、「どこ?」と間宮。
「白里海岸です」
「あんた、何言ってんだか、全然分かんないよ」
不貞腐れた態度で、再び、「あんたの話が聞きたい」と繰り返す。
「僕はもう話しました」
「そう。覚えてないな」
「僕は小学校の教師。家族は妻が一人です」
「奥さん、何してんの?」
「何もしてません。単なる主婦ですよ」
「誰が?」
「僕の妻です」
「ああ、ピンクのネグリジェの女か」
「…見てたんですか?」
「俺には、何も思い出せない。思い出すのはあんただ」
花岡は間宮が点けたライターの火を見つめる。
「ね、奥さんの話、もっと聞かせて」
一方、高部は仕事が終わり自宅に戻り、用意された夕食を温めようとすると、今日は調子がいいと起きてきた妻の文江が支度を始めた。
文江は精神疾患で、佐久間に紹介された精神科医のカウンセリングを受けている。
冒頭の女性である。
そんな文江を心配する高部は、今回の事件が終わったら、旅行へ行こうと誘う。
 |
| 文江 |
再び事件が起きた。
見知らぬ記憶喪失の男を自宅に呼んだ花岡は、その後、妻を一連の事件と同じ手口で惨殺し、窓から飛び降りて失神したのだった。
佐久間を連れた高岡は、病室の花岡に、なぜ妻をあんな殺し方をしたかについて尋問する。
「分かんないんです。どうしてあんなことに」
 |
| 花岡 |
「なんか、小説で読んだとか、映画で見たとか…誰かから聞いたとか」
首を横に振る花岡に、佐久間は、「奥さんとうまくいっていなかったんですね?」と追求するが、花岡はそれを否定する。
「自分がやったことは全部覚えています。確かに僕が倫子を殺しました。あの時は、ああするのが当然だと思ったんです」
「喧嘩でも?」
「…理由はありません」
花岡は泣き崩れ、叫んで壁に突進して、ワゴンに頭を打ち付ける。
「ただ魔が差したっていうだけで、人間はあんな風に刃物を使えるもんかな。例えばさ、犯人たちは幼児期に、同じトラウマを背負った。で、それが潜在的に憎悪となって爆発した。そういうのって、あるか?」
「いつから精神科医になったんだ」
「文江のことで、その手の本を読んでみた。笑うな。入門書程度だ」
「本に書いてあることなんて、信用するな。犯罪の動機なんてのは、所詮、他人には分からん。時に本人もな。ってことはつまり、誰にも分からんってことだ…深入りし過ぎるなよ、人の心に」
「そんなつもりはない。俺はただ、犯罪を説明する言葉を探してる。それが俺の仕事だ」
そんな折、間宮が屋根の上に立ち、巡回していた大井田巡査が止めに入るが、飛び降りて捻挫をした間宮を交番に連れて行く。
調書を取ろうとするが、同じことを何度も質問してきて、前に進まない。
タバコを吸ってもいいかと聞き、大井田も一緒に吸い始め、同僚はパトロールに出て行った。
眠いと言って間宮は机にうつ伏せるが、ライターに火を点け、大井田に「これ見て…俺さ、あんたの話が聞きたい」と声をかける。
 |
| 大井田巡査 |
ライターの火を見つめる大井田。
翌日、間宮は病院に連れて行かれ入院した。
その直後、大井田は、自転車で出かけようとする部下の頭部をいきなり背後からピストルで撃ち、刃物を持って交番の奥へ遺体を運んだ。
 |
| 後方から発砲する大井田巡査 |
そんな折、文江は精神科への道に迷い、遅れて病室に入ったが、担当医に覚えているかと渡された『青髭』を見たこともない本だと答える。
【以下、17世紀ヨーロッパに生きたフランスの詩人シャルル・ペローの「童話集」にある、「青ひげ」の紹介。
「青髭」と呼ばれ、恐れられていた富豪がいる。彼はこれまで6回結婚しながら、彼女らは全て行方不明になっていたにも拘らず、7回目の結婚をする青髭。そんな青髭が外出することになり、件(くだん)の新婦に部屋の鍵を渡す際に、「この小部屋にだけは絶対に入るな」と言って外出する。しかし、新婦は好奇心を抑えられず、小部屋を開けてしまって驚嘆する。そこには、行方不明になっていた6人の先妻の遺体が隠されていたのだ。帰途した青髭は新婦が立入禁止の小部屋を開けたことを見抜き、殺害せんとするが、兄と図った新婦は、兄が率いる兵士らによって青髭は殺されるに至った。かくて新婦は、青髭の遺産を全部手に入れて金持ちになったという話である】
 |
| ギュスターヴ・ドレによる青髭の挿絵(ウィキ) |
.jpg) |
| シャルル・ペロー(ウィキ) |
この「青髭」の話を知らないと答える文江には深刻な記憶障害が見られる。
一方、間宮は内科医の宮島に、「不安は?」と聞かれ、「不安はあんたの方にある」と答え、禁煙だと分かると、水をコップに入れ、話し始める。
 |
| 宮島 |
「前は、俺の中にあったものが、今、全部外にある。だから、先生の中にあるものが俺には見えるんだよね。その代わり、俺自身は空っぽになった」
間宮は水を入れたコップを倒し、水が床の上を広がっていくのを宮島は凝視する。
「今度は、先生の話、聞かせてよ…どうして医者になったの?…女のくせに」
「女のくせに?」
顔を上げた宮島の頭を押さえる間宮。
「“女のくせに”、よくそう言われなかった?よくそう言われたよね。思い出して、その時の気持ちをはっきりと…女は男より、下等な生き物だ。違う?」
顔を横に振る宮島。
間宮は、学生時代の死体解剖で、初めて男性遺体をメスで切り刻んでいて、胸がすっーとしたのではないかと、宮島に思い出すようにと語りかける。
「…あんたは本当は外科医になりたかった…違う。あんたが本当に望んだことは、男を切り刻むことだ」
そこで、残りのコップの水を宮島の顔にかけた。
間宮が出て行ったあと、宮島は壁に書かれたⅩの文字を見る。
その頃、取り調べで大井田は、同僚が憎かったと動機を話したが、高部と佐久間に詰問されても、灯りを見せられたことや、誰かがいたことすら覚えておらず、唐突にスティックで刑事の首から胸にⅩ字をなぞって、そのことを指摘されると、少し記憶を取り戻してきた。
 |
| Ⅹ字をなぞっていく大井田 |
また、中央公園の男子トイレで、宮島は男の首をⅹ字に切り裂いて惨殺する。
洗面台には水が溢れていた。
江東区の潮見町病院に、3日前に大井田が連れて来た不審な人物がいるとの情報が入り、高部は急ぎ病院へ向かうが病室にはおらず、院内を探して、ようやく間宮を見つけるが、声だけで、なかなか姿を現さない。
「あんた、誰だ?」
「警察です」
「誰?…俺の質問の意味、分かってる?」
「あなたに、お伺いしたいことがあります」
「俺は、あんたの話が聞きたい」
「こっちが、聞きたいんだ!ちゃんと、答えろ!」
高部が大声で怒鳴りつけ、他の警察も来て、間宮はようやく取調室へ連れて行かれた。
間宮は、相変わらず、何から何まで知らないと答えず、犯人の写真を見せても、覚えていないと言うので、花岡の家で指紋が検出されたと指摘する。
「あなたが覚えていなくても、あなたはこの花岡と会っているということです」
「ああ、そういうことか。何でも知ってんだね、刑事さん」
「あなたの頭の中までは分かりません」
「頭…ここか」
間宮は高部の額に人差し指を突きつける。
「そういう態度は、あなたのためになりませんよ」
「なんで?」
高部は極力感情を抑え、質問を続けるが、それに答えず、タバコを吸っていいかと訊かれた瞬間、激昂して間宮が座ろうとした椅子を思い切り叩く。
佐久間が部屋に入って来て、高部を諫(いさ)める。
「刑事さん、あんたの話、もっと聞かしてよ」
高部が殴りかかろうとするので、佐久間は部屋から連れ出す。
佐久間は、典型的な精神障害の症状が見られるから、まともに相手にするなと忠告する。
自宅に帰ると文江がおらず、高部は近所を探して、買い物の帰りの道に迷った文江を見つけた。
夫が疲れていることを気にかける文江を、何としても旅行に連れて行くと抱き寄せる。
高部は、参考人である間宮を容疑者扱いして服を脱がせると、背中に大きな火傷の跡があった。
間宮の自宅の手掛かりを得た高部は、廃屋のようなビルの住居に辿り着く。
大家に訊くと、家賃を前払いしている間宮を最後に見たのは半年ほど前とのことだった。
部屋に入ると、本棚に数多くの心理学や精神医学の本が並び、机の上には催眠療法を発明したメスマーの本が置かれていた。
更に、間宮が書いた『動物磁気とその心理作用についての考察』という論文の草稿が見つかる。
【メスマーとは、動物磁気説を唱えて暗示療法を行ったオーストリアの医学者】
そして、浴室のシャワーには、両手両足をクロスして紐で引っ張られた猿のミイラが括りつけられていた。
高部は間宮について調べたことを、電話で佐久間に伝えた。
「名前は間宮邦彦。3年前まで、武蔵野医科大精神科の学生だった男だ。教授に聞いてみたら、研究室には殆ど顔を出さなかったらしい…それと、川崎の廃品回収センターでバイトやってる。肩の火傷はその頃のものだろ。行方不明になって半年だ」
高部はメスマーについて佐久間に帰ってから聞くと電話を切るが、ふと、間宮の部屋で見た浴室の猿のミイラと共に、文江のことが脳裏を過(よ)ぎり、気になって自宅に戻る。
急いで部屋に入ると、文江が首吊り自殺をしていた。
それを見た高部は衝撃を受け、両膝をついて両手で顔を覆う。
しかし、それは幻影だった。
調理をしていた文江が心配して高部に声を掛ける。
「びっくりしちゃった。具合でも悪いの?どうして、こんな時間にいるの?」
「別に、ちょっと」
そう答えて署に帰った高部は、間宮を病院へ移送したと佐久間に聞かされる。
「誰の権限でそんなことした!あいつを俺から引き離すつもりだな」
「そうだ。お前がこれ以上、あの男と話すのは危険だからだ」
高部はその足で、メスマーについて間宮に聞きに病院を訪れた。
面会謝絶の部屋に強引に入り込んだ高部。
「メスマーって、何者だ?」
「誰?」
「お前は、武蔵野医科大の精神科でメスマーと催眠暗示について研究していた…お前が覚えていようがいまいが、俺は調書を作って、お前を正式に逮捕し、殺人教唆で送検する…それで終わりだ」
高部はそれだけ言うと、溜息をつきながら椅子に座る。
「あんた、奥さんが死んでる姿、想像したろ?」
驚いて間宮の顔を見る高部。
「あんたの女房、病気なんだってな。自宅で世話するのは大変だろ」
「それ、どこで聞いた?」
「教えてくれたよ、若い刑事が…嫌か、女房の話」
「まあいい。時間はいくらでもある。ともかく、お前はもう逃げられない」
「逃げ出したのは、あんたの方だ…俺に何でも話してみろ。そのために来たんだろ」
高部はそれに答えず、犯人たちにどうやって暗示をかけたかについて間宮に聞いていく。
間宮は、「刑事のあんたと、夫としてのあんたと、どっちが本当のあんたなんだ?」と話を引き戻す。
「どうやって暗示をかけたんだ」と高部も同じ質問を続ける。
「どっちも本当のあんたじゃないよな。本当のあんたはどこにもいない。それは女房にも分かってる」
高部は、「どうやって暗示をかけたんだ」と、何度も質問を繰り返す。
間宮が「見ろ」とライターに火を点けると、高部はそれを手で叩き落とした。
「ああ、そうだよ。女房は俺の重荷だ。お前に言われなくても分かってるんだよ、そんなことは!…俺にはアイツの心が分からない。アイツも俺のこの苦しみは分からない。そうなったのは、皆、俺の責任だと分かってるよ。だから、どうだってんだ!」
「そうするよりしか、なかったんだろ?」
「そうだよ!他にどうすりゃ良かったんだよ!いいか、俺はこれでいいと思ってる。人間はこうあるべきだと思ってる。気ままに、楽しく、平和に人生を送る。冗談じゃない!社会は、そんな風になってないじゃないか!」
「ああ、社会が悪い。そういうことか」
「お前みたいな奴がいるからだ。お前みたいな犯罪者がいるから、俺の頭はいつもピリピリ、ピリピリ、ピリピリ、射合ってるんだ!何で、お前みたいな奴が楽して、俺みたいなまともな人間が苦しまなきゃならないんだよ!あんな女房の面倒を、一生見なきゃいけないんだ!」
高部は感情を荒げ、本音の思いを吐き出してしまい、頭を抱えるのだった。
「お前なんかいなきゃ、俺だって女房と上手くやっていけたんだ。俺は女房を許す。だが、お前たちは許さない」
「すごいじゃない」
「面白かったか?俺の話」
「ああ」
「よし、今度はお前の番だ。たっぷりしゃべってもらうぞ」
ライターの火を点ける高部。
「すごいよ、あんた」
しかし、雨が降り出し、天井からの雨漏りで火は消え、流れる水を見つめる高部。
「その水が、あんたを楽にする。気持ちいい。空っぽだ。生まれ変われ。俺みたいに」
見張りの刑事がドアを開けると、高部が出て来て、部屋で間宮が床に横になっていた。
高部は文江のことを間宮に話した当該刑事を、殴る蹴るの暴行をする。
 |
| 「お前か?あいつに俺のこと喋ったのはお前か?」 |
まもなく、間宮は警察幹部たちの前に高部と共に座り、質問を受ける。
「あんた誰だ?」
「本部長の藤原と言いますが。どうです、間宮さん。あなた今、なんでこんなところにいるのか分かってらっしゃいますか?」
「なに?」
「なにじゃないでしょ、ちゃんと答えなさい」
「なにが?」
間宮は隣の高部に、「あんたの上司?」と訊く。
「ああ」
「つまらない男だ」
「間宮さん、私の質問に答えなさい」
「あんた誰だ?」
「本部長の藤原です。おい、ふざけてるのか!」
「誰だ?」
「高部、なんなんだ、この男は…」
「いいか、もう一度聞くぞ。本部長の藤原。あんたは誰だ?」
「君、私の何が聞きたいんだ?」
「それは自分で考えろ」
藤原は呆然として引き下がり、一部始終を聞いていた他の警察幹部も混乱する。
間宮は高部に囁く。
「最低だな。あいつら、何も分かってないんじゃない。俺のことも、あんたのことも。刑事さん、俺の声、聞こえてる?聞こえてるよね。それがあんたが特別な人間である証拠だ。初めから分かってたでしょ。俺は分かってた。あんた、あの連中とは違う」
高部が間宮の顔を見る。
高部は間宮の顔を手のひらで掴み、椅子ごと後ろに撥ねつけた。
異様な状況に、出席した警察幹部は動揺を隠せないようだった。
2 「思い出したか?全部、思い出したか?」「そうか。これでお前も終わりだ」
帰宅した高部は、空のまま作動している洗濯機のスイッチを切り、ダイニングテーブルの上の皿の蓋を開けると、生のステーキ肉があって言葉を失う。
文江が起きてきて、無言でまた洗濯機のスイッチを入れ寝室に戻り、高部はまた、そのスイッチを切り、生のステーキ肉を思い切り壁に投げつけた。
文江の眠る寝室のナイトテーブルには複数の沖縄行きのパンフレットが散らばり、ベッド脇に旅行用バッグが2つ置かれている。
それを見た高部が、キッチンのナイフに手が伸びる画がインサートされる。
その後、高部は文江を病院へ連れて行き、仕事が落ち着いたら迎えに来ると担当医(院長?)に伝えた。
「働き過ぎは決していいことじゃありません。私から見ると、奥さんより、あなたの方が病気に見えます」
ファミレスで殆ど食事を残し、片付けてもらったところで携帯に電話が入り、佐久間が高部を自宅に呼んだ。
催眠治療の記録フィルムが手に入り、それを高部に見せる。
撮影されたのは恐らく19世紀末で、女性患者に向かって、手でⅩの字を書いているように見える。
「どういうことだ?」
「この女の名は村川すず。ヒステリー患者。記録に残ってるのはそれだけだ。警察の資料によると、1898年、村川すずは自分の息子を殺害して、逮捕されている。で、その手口なんだが、首筋を十文字に切り開くというものだったらしいんだな。それ以上のことは分からない」
「間宮もこのフィルム見てるのか?」
佐久間はその可能性を否定し、見ていたとしても間宮の行動を説明することにはならないだろうと言うのだ。
高部はカメラの前の男が誰なのかと聞くが、それも分からないが、カメラに映らなかった理由は分かると話す。
当時、催眠術は霊術と言われ、こういうオカルティズムは、いつの時代も権力の弾圧を受けた。
「だからこの治療も、明治政府の目を忍んで、密かな儀式として行うしかなかったんだろうな」
その話をしながら、佐久間は回想と妄想に意識が囚われていく。
佐久間は間宮の自宅を訪れ、『邪教』という本を手に取ってページを捲(めく)り、顔がのっぺらぼうのような、霊術師の伯楽陶二郎という男の顔の画像を目にする。
その後、辺境の地の古びた木造の廃病院を訪れ、更に、間宮の元を訪れた。
部屋に入ると間宮はおらず、間宮の家にあった手足が捻(ねじ)れた猿のミイラがあり、振り返ると暗がりから高部が近づいてくる。
「佐久間、佐久間」と声をかけられ、正気を戻す。
「で、間宮は一体何者なんだ?お前の推測でいい。聞かせてくれ」
「伝道師…世の中に、知識を広めるための…いや、これは、俺の妄想だ。何言ってるんだろな、高部、俺の言うこと真に受けるな。ちょっと疲れてんな。今日は、これぐらいにしよう。俺が深入りしてちゃ、シャレになんねえな」
電気を付けた隣の部屋を見ると、壁にⅩの文字が書かれている。
「佐久間、何だそれ?」
「いや、これか。何かの参考になると思ってな」
佐久間は立ち上がって、それを必死で消そうとする。
「何の参考だ?」
「いや、何だろう。俺にもよく分からない」
「お前、間宮に会ったな」
「おかしいよな…思い出せないんだよ」
間宮が病室で椅子でヒーターを打ち続けて暴れ、高部が駆け付けると、監視の刑事は殺され、間宮は逃走していた。
佐久間の自殺の報を車で受けた高部は自宅へ向かい、鑑識から自ら首筋を切ったことを知らされるが、顔色一つ変えることはなかった。
高部はその足で、辺境の廃病院へ向かい、ドアを壊して中に入ると、ビニールのカーテン越しに人影が見える。
カーテンを開けると、佐久間が本で見た伯楽陶二郎のぼやけた顔写真だった。
 |
| 【伯楽陶二郎は明治時代に存在した精神医療グループ「気流の会」のリーダーと言われ、催眠暗示の思想を持っていたとされるが、詳細は不明】 |
奥の部屋の壊れたベッドに俯(うつむ)いて座る高部の元に、この廃病院で待っていた間宮が声をかける。
「やっと来たね、刑事さん。どうして俺を逃がしてくれたの?分かってる。俺を逃がして、俺の本当の秘密を突き止めたかったんだ…そんなことしなくてよかったのに。本当の自分に出会いたい人間は、いつか必ずここへ来る。そういう運命なんだ」
徐(おもむろ)に立ち上がった高部が、間宮に銃丸を3発撃ち込む。
「思い出したか?全部、思い出したか?」
倒れた間宮は、高部の顔を見ながら頷く。
高部に指を差し出し、Xの文字を描く間宮に、高部は数発銃丸を浴びせた。
その後、高部は伯楽陶二郎と思われる録音テープの音声に聴き入る。
文江が何者かに首をXに切り裂かれ、殺害された。
ラスト。
いつものファミレスで食事を完食し、仕事の電話を受け応えする高部は活き活きとした表情を浮かべている。
コーヒーを運んで来たウェイトレスが、食器を片付け、上司から何やら耳打ちされると、一瞬考えてからホールの奥へ行き、包丁を手にして歩き始めた。
 |
注意されたあと、考え込むウェイトレス
 |
左にナイフだけ手に持つウェイトレスの画が見える(上はナイフのみの画像) |
3 最強の伝道師
間宮は医学生時代にメスマーの影響を受け、催眠術と読心術を身につける。
 |
| フランツ・アントン・メスマー(ウィキ) |
その過程で自身も空っぽになり、記憶も失うが、そのことで相手の潜在意識に侵入し、催眠をかけて封印された憎悪を引き出していく。
引き摺り出された憎悪が一気に膨れ上がって、特定他者に対する殺人の儀式を遂行させていくのだ。
全て同じ手口である。
人は誰しも何某かの矛盾と葛藤し、フラストレーションを抱え、時に憎悪の感情も潜在化させている。
だからと言って、それが表面化し、行為に振れるに至らず、封印することで日常生活を平穏に保つことに成功している。
間宮はそんな小さな憎悪や矛盾した感情にアクセスして催眠にかけ、本来、必然性がない殺人へと駆り立てる。
「アクティングアウト」(無自覚な葛藤の「行動化」)である。
 |
| アクティングアウト(YouTube) |
その典型は、間宮が入院した時に担当した宮島女医のエピソード。
宮島は学生時代の死体解剖で、初めて男性遺体をメスで切り刻んでいて、胸がすっーとしたのではないかと指摘して、間宮は催眠中の宮島に言い切った。
「…あんたは本当は外科医になりたかった…違う。あんたが本当に望んだことは、男を切り刻むことだ」
催眠をかけられた宮島が、程なく事件を起こすに至るという経緯である。
思うに、この種の催眠法が信仰のように経典化され、儀式化され、伝道されていくとしたら恐るべきことである。
間宮は繰り返し、相手に誰なのかを問い、本当の自分について語らせようとする。
 |
| 催眠を受け、妻を殺し、悔いる花岡 |
そして、それを言わされ、自分の中の潜在的な感情を発見した相手は、それが本当の自分であると確信し、その感情を最大化して行動を起こさせるのである。
本人は殺人の記憶はあるが、それがどうして行動化されたかについての記憶がない。
間宮によって催眠をかけられているからだ。
それが殺人教唆として、高部は逮捕しようと間宮に接することで、自らの妻を疎(うと)む思いを吐露するが、それは高部にとっては自覚的なことであり、自分が誰で、何者かを知っているが故に、高部には間宮の催眠は通じなかった。
通じないどころか、逆に間宮をコントロールし、より強固な催眠術を身につけ、負担だった妻からも解放され、同じようにフラストレーションを抱えた周囲を動かし、新たな伝道師として生まれ変わっていく。
ラストシーンで描かれたように、店員とのアイコンタクトのみで店の風景を変えてしまう高部こそ、最強の伝道師である。
以上の文脈で言えば、間宮の催眠によって、精神科医である自己の脆さを引き出され自死に至る佐久間の結末には悲哀を覚えざるを得なかった。
また妻の文江を殺害したのは高部の可能性があるが、間宮のように一連の手続き(「あんたの話を聞かせて」という話法や、光や水というアイテム)を経なければ相手に行動を起こさせることができない瑕疵を有する能力とは無縁に、アイコンタクトのみで高度な催眠法を駆使できるので、高部の直接的な妻殺しは否定できるだろう。
恐らく、病院の院長と思われる文江の担当医から「私から見ると、奥さんより、あなたの方が病気に見えます」と言われた際に、院長を凝視するカットがあったが、このアイコンタクトのみで催眠を駆使したものと思われるのだ。

今や存在価値のない間宮を殺害した高部が、最強の伝道師たる所以である。
間宮もそれを分かっているから、高部から銃撃された際に「思い出したか?全部、思い出したか?」という問いに対して、高部の顔を見ながら頷いたのである。
間宮はその程度の「悪意ある伝道師」だったということだ。
思うに、人間の自我の脆さ・無自覚さ・無防備さ・被暗示性の高さなどによって誘導されるままになり、悪意ある伝道師に騙されてしまうのは、さながら、現代におけるディープフェイクに洗脳され、殺人事件まで惹き起こしてしまうメンタリティに通じるものがある。
それは決して催眠状態にあるわけではないが、人間の認知に入り込む危うい情報の束、即ち「確証バイアス」(自分に都合のいい情報のみを取り入れる傾向)の強さによって感情・行動が一定方向に動員される情況において、過分な自己肯定感と昂揚感を生み、自分が何者かを知ったつもりになって行動化するに至るのは、催眠状態に近い感覚麻痺の如き様態と言えるかも知れない。
そんな人間の心の脆さ・危うさを映画的に提示した問題意識が、この作品から読み取ることができる。
―― それにしても役所広司の演技力の凄みに圧倒される。
(2025年7月)




















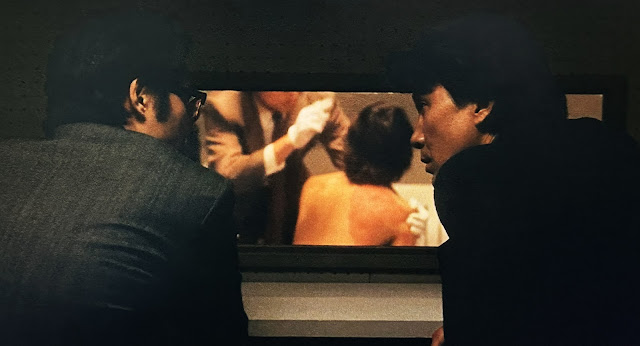












































0 件のコメント:
コメントを投稿