1 「瞳は語りかける。瞳は雄弁だ」
【現在】
「1974年6月21日 モラレスとリリアナの最後の朝食。モラレスはこの朝を生涯忘れない。休暇の計画を立て、咳に効くレモンティーを飲んだ。角砂糖は、いつも通りひとつ半。以来、ベリージャムは食べてない。花柄のパジャマ。そして彼女の笑顔。目覚めたばかりの笑顔。左の頬に朝日が降り注ぐ。そして…」
 |
| リリアナ |
そこまで書いた小説の原稿を破り捨てた男。
寝る間際に、「“怖い”」と一言メモに残す。
男の名は、ベンハミン・エスポシト(以下、ベンハミン)。
 |
| ベンハミン |
元連邦最高裁判所調査官である。
定年退職したベンハミンは、25年前に担当した、強姦殺人事件を題材にして、小説を書こうとしているのだ。
当時、判事補で、自分の上司だったイレーネを訪ね、当該事件について話を聞きに来る。
 |
| イレーネ(左)とベンハミン |
【過去】
判事補のロマーノに否応なしに、その殺人事件を担当させられ、現場に行って遺体を見たベンハミンは衝撃を受ける。
被害者の名はリリアナ・コロト(以下、リリアナ)。
23歳で教師のリリアナは、新婚直後だった。
銀行員の夫の名は、リカルド・モラレス(以下、モラレス)。
二人の職人が犯人として逮捕されたが、拷問による自白の強要であることを知り、ベンハミンが担当のロマーノの不正を訴えたことで、ロマーノはブエノスアイレス郊外にあるチビルコイに左遷されることになる。
その後、モラレスを訪ねたベンハミンは、彼から質問を受ける。
「犯人が捕まったら、どんな刑を?」
 |
| モラレス |
「暴行殺人は終身刑だ。この国に死刑はない」
「死刑には反対だ」
「私も反対だ。ただ少しでも気が治まるかと」
「気が治まる?奴を暴行し、殺すのか?違うだろ。注射で永遠に眠らせるだけだ。羨ましいくらいだ…犯人には、長生きして欲しい。空虚な日々を生きて欲しい」
ベンハミンがモラレスにリリアナのアルバムを見せてもらっていると、あることに気づく。
リリアナを見つめている男が写っていたのである。
その男の名は、イシドロ・ゴメス(以下、ゴメス)。
 |
| ゴメス |
【現在】
小説に書かれたあらすじをイレーネに読んでもらった。
「写真の件は信じがたいわ」
「そうかもな。問題は、彼の眼差しだ。奴の彼女への想いは、瞳に表れている。瞳は語りかける。瞳は雄弁だ」
【過去】
モラレスは、ベンハミンの指摘から、ゴメスの実家に電話して、所在を確かめる。
ゴメスの母親にリリアナについて尋ねたら、「仲良しだったわよ…大好きだったからね」という答えだった。
ゴメスがブエノスアイレスの建設現場で働いていると聞き出し、その情報を元に警察が向かうが、既に引き払った後だった。
ベンハミンは、同僚のパブロを連れ、ゴメスの母親の住む実家に入り込み、タンスの引き出しからゴメスからの手紙を見つけ出す。
 |
| パブロ(左) |
持ち帰った手紙を分析するが、何にも手掛かりを掴めない。
判事に呼ばれたベンハミンとパブロは、実家のある連邦警察からの通報で、行き過ぎた捜査を知られ、叱責されるのだ。
 |
| 判事(左) |
イレーネから本件の撤退を告げられたベンハミン。
【現在】
ベンハミンとイレーネは、イレーネの婚約パーティーの写真を見ている。
その中の一枚に、イレーネを見つめるベンハミンが写っていた。
「瞳は雄弁だ」と吐露したベンハミンの言葉が想起される。
「別人みたいだ」
「いい小説になるわ。でも私は読めない。あなたは過去を振り返りたくても、私にはできない。毎日、仕事がある。これが“正義”かはわからない。でも“正義”のひとつよ。仕事を終え、帰宅して、夫との生活があり、子供たちがいる。私は常に前を向いてきた…厄介ね。変われないの」
【過去】
事件から一年経った頃、ベンハミンは駅で犯人を捜すモラレスに再会する。
 |
| ゴメスを捜し続けるモラレスを見て、驚くベンハミン |
「火曜と木曜がこの駅…他の曜日は別の駅で捜す。曜日は月ごとに変える。いつか通る。首都を警戒して、郊外にいるはずだ。事件から1年だが、捜査は続いてますよね」
「もちろんだ」
「異常に見えます?」
「そんなことは」
「忘れるのがつらい。努力しないと忘れる。事件の朝、レモンティーを飲んだ。彼女が作ってくれた。些細なことを思い出す。だが、それも曖昧になる。蜂蜜入りの紅茶だった気もする。記憶が薄れていくんだ」
その翌日、ベンハミンはイレーネを訪ねた。
「昨日、あることがあって、一晩中、眠れなかった。あなたのことを思った。現実を別の角度から見たんだ。他人を見て、自分の人生を見つめ直した…こう考えた。イレーネに話そうと。もしかしたら、殺されるかもしれない。だが試そうと」
そこに、パブロが加わった。
「駅でモラレスに会った。何してたと思います?」
「わからないわ」
「駅で毎日、犯人を捜してるんです。仕事の後、毎日ですよ」とパブロ。
「彼の愛は並みじゃない。感動的です。妻の死が、彼の時を永遠に止めた。わかります?彼の瞳を見るべきだ。あれこそ真の愛だ。想像できますか?日常に汚されず、義務感に縛られない」
「私とは無縁ね」
「彼にチャンスを与えたいんです」とパブロ。
「それで?」
「捜査を再開する必要がある」
「判事と私の署名入りの書類を破棄しろと?捜査は続いていると、内容を改ざんするの?」
「いい案だ」
「バカ言わないで」
その後、パブロは「好きなものは変えられない」と言うや、手紙の内容からアルゼンチンの国技と言っていい、彼のサッカーへの情熱の深さに注目する。
かくて、ベンハミンとパブロは、サッカー場に通い続け、遂にゴメスを見つけ出し、拘束するに至る。
 |
| ゴメス(手前)を見つけ出すベンハミン(左) |
ゴメスを追求するベンハミンだが、決め手はなかった。
そこに、証拠もなしに拘束することに反対するイレーネが入室して来た。
ベンハミンに話しかけるイレーネは、自分の胸を凝視するゴメスの瞳に気づく。
 |
| ゴメスの瞳に気づくイレーネ |
この時、イレーネが取った行動が、物語の本線を再構築していくことになる。
彼女は、この男が犯人じゃないと言い切り、被害者のリリアナの遺体写真を見せながら、犯人は「剛腕で強靭な肉体の持ち主」だったからと、ゴメスのひ弱な身体を揶揄する言葉を並び立て、挑発していくのである。
「スパゲッティみたい。この男のアレは、ピーナッツ程度よ」
そこまで愚弄されたゴメスは、立ち上がって自分のペニスを出し、イレーネを売女呼ばわりするのだ。
怯(ひる)まず、イレーネは挑発する。
「いいこと?高望みはしないで、おチビさん。精力もないくせに」
「精力がないだと?どうやったか見せてやる!あの女。めちゃくちゃにしてやった」
そう叫び、イレーネを殴りつけるのだ。
ベンハミンがゴメスの胸倉を掴む。
「彼女に触れたら殺す」
拷問せずに、自白に追い込んだのである。
ベンハミンは、今日も駅で犯人を捜すモラレスに、ゴメス逮捕の知らせをもたらした。
【現在】
イレーネからの電話。
「小説、完成したら読ませて」
【過去】
結婚式が迫るイレーネだが、浮かない顔をしている。
テレビを観ていたモラレスは、あることに気づき、ベンハミンに電話をかける。
テレビを点けると、施設訪問する大統領のニュース映像に、大統領のボディーガードをするゴメスが映っているのだ。
 |
| イサベル・ペロン大統領の右側にゴメスが映っている |
直ちに、ベンハミンはイレーネと共に、かつて暴力的な自白強要をベンハミンに告発され、チビルコイの裁判所に左遷されたロマーノに会いに行き、行政命令によるゴメスの釈放について問い質す。
「君たちのいる世界は狭い。君たちは小鳥を追い、我々はジャングルで戦っている。ゴメスは、服役中に我々に協力し始めた。ゲリラの情報をつかんだりした。いい仕事をした。何か不満かね?」
「事態を理解してます?殺人犯なんですよ」とイレーネ。
「かもしれん。だが賢い勇敢な男だ…悪人も役に立つ」
「判事が逮捕を命じたんですよ」とイレーネ。
「俺への腹いせに釈放したな。バカにしてるのか」
怒気を荒げるベンハミンの言辞を無視し、ロマーノはこの件に関わらない方がいいと忠告する。
「何をやっても無駄ですよ…大学の知識がすべてじゃない」
反応できないイレーネ。
今度は、ベンハミンに問い質す。
「なぜ彼女と来る?自分を守るためか?彼女は、お前とは関係ない。彼女は法学博士だが、お前は高卒だ。金持ちと貧乏人。価値のある人間と、ない人間。彼女は守られてる。お前は違う。生きる世界が違うんだ。俺に文句があるなら、1人で来い」
何も言い返せないベンハミンは、イレーネと共に去る。
あろうことか、エレベーターに乗ると、ゴメスが入り込んで来た。
無言で、わざとらしく拳銃の引き金を引いて見せるゴメス。
挑発されて自白した男が、今度は挑発した者を挑発するのだ。
2 扉を閉めさせる女と、部屋に入っていく男
【過去】
モラレスに会うベンハミン。
「終身刑では?」
「そのはずだった」
「では、どうして?」
「正義を行う者がいない」
その後、イレーネに仕事が終わった後、食事の誘いを受けたベンハミンだったが、アルコール依存症のパブロがバーで警察沙汰となり、自宅に連れて帰ることになった。
パブロの妻を呼びに行き、戻って来ると、パブロは何者かに惨殺されていた。
 |
| 衝撃を受けるベンハミン |
「狂気の沙汰だ」
「身を隠すのよ…ロマーノの仕業よ」
イレーネは地元でのベンハミンの仕事を見つけ、列車で送り出す。
「無理だ。イレーネ。俺の人生のすべてはここにある。人生のすべてだ」
「どうするの?ここで、私たち。つまり、あなたと私…何もできないわ」
二人は瞳を見つめ合い、頬を寄せ合うが、ベンハミンは抱き締めることもできず、一言添えるのみだった。
「さようなら」
【現在】
第一稿を書き上げ、イレーネに読んでもらうベンハミン。
感想を聞かれたイレーネは、最後のシーンについて捲(まく)し立てる。
「小説だから、真実を書く必要はないけど、あの場面はなに?男がフフイ(アルゼンチン北西端部の都市)へ旅立つ所よ…まるで未来は、灰色であるかのように。まるで最大の愛を告白できなかったかのように」
「その通りじゃないか」
「だとしたら、なぜ1人で去ったの?…いくじなし」
その後の小説の後味の悪い展開について話した後、ベンハミンは吐露する。
「同じ過ちを繰り返したくない。何かしたい。25年間、自問自答を繰り返してきた。忘れろ。すべては過去だ、考えるなと。だが、できない。過去じゃない。今も続いている。知りたい。この虚しさは何だ。この空虚を、どう生きればいい。どうすればいい」
二人は役所を訪れ、ゴメスとモラレスの所在を探し出した。
ベンハミンは、一人でモラレスの家を訪ねていく。
相変わらず銀行に勤め、再婚はしていなかった。
小説を読んで、驚くモラレス。
しかし、この事件が忘れられないと言うベンハミンに対し、モラレスは絶対に忘れるべきだと言い放つ。
「その後、ゴメスは?ああいう奴は逃げ切る」
「どうしても、わからないことがある。彼女の不在にどう耐えた」
「25年経ったんですよ」
「耐えられないかと」
「25年が経った」
「どうすれば、やり直せる」
「25年が経った!忘れるべきだ」
同じ質問を繰り返すベンハミンに対し、モラレスは声を荒げて反発する。
「何を知りたい」
「なぜ耐えられるのか」
「何もできない」
「1年も駅で待ち続けたあなたに?」
「犯人は釈放された。どうしろと?」
「それですべて終わり?あなたは聡明だ」
「だから?私の人生だ」
「そうじゃない。私の人生でもある。あなたの愛は本物だ。稀にみる愛だ。他にはない、真の愛だ」
ベンハミンを凝視した後、モラレスは突っぱねるように言った。
「帰ってくれ。今すぐ。私の人生だ。あなたのじゃない」
「悪かった…私も年を取った。年のせいだ…パブロを殺したのはゴメスじゃない」
「それで?」
「ゴメスは私を知っていた…罪悪感から、墓参りにも行ってない…」
「選択に気を付けて。思い出がすべてだ。マシな方を選んで」
「どうしても忘れられないことがある。パブロの最後の言葉だ。“心配するな。犯人を捕まえてやる”。私が捕まえる。生きていればな」
「待って。どうか座って…探しても無駄だ。司法は何もしない。奴は守られてる。だが必ず姿を現すと思った。あなたを殺しに…」
ここでモラレスは、ベンハミンの家に現れたゴメスを急襲し、拳銃で射殺したことを告白する。
「気が済んだ?」
「忘れるんだ。忘れるべきだ。考えても無駄だ。妻は死んだ。パブロも死んだ。ゴメスも死んだ。もう終わった。いろいろ想像しても、無意味だ。過去に囚われ、未来を失う…思い出に惑わされる」
帰途についたベンハミンの脳裏には、これまでの事件にかかわった者たちの言葉が次々に過(よぎ)り、ふと浮かんだ疑念から、モラレスの家に引き返した。
 |
| ベンハミンはパブロのこの言葉を想起し、モラレスの家に引き返していく |
そこでベンヤミンが発見したものは、檻に入れられ、老いたゴメスの姿だった。
 |
| ベンハミンに気づくゴメス(中央)とモラレス(右) |
モラレスはゴメスに対して、冷たい視線を放つのみ。
「終身刑ですよね」
モラレスの言辞である。
モラレスの執念に圧倒されたベンハミンは、無言で立ち去っていく。
地元に戻ったベンハミンは、やっとパブロの墓参りをし、小説を完成させた。
かつて、走り書きした「“怖い”」を「“愛してる”」と書き換えたベンハミンは、イレーネの元に走る。
「生きてたのね」
「話がある」
ベンハミンの瞳を見てイレーネは、全てを察する。
「簡単じゃないわよ」
「構わない」
微笑みを交わす二人。
「扉を閉めて」
そう言って、扉を閉めさせる女と、部屋に入っていく男。
ラストカットである。
3 息を呑む圧巻の心理的リアリズム
凄い映画だった。
この映画を知らなかったことに対して、忸怩(じくじ)たる思いが残るほどである。
圧巻の心理的リアリズム ―― そこに加える評価の何ものもない。
―― 以下、批評。
「お願いだ…彼に言ってくれ。話しかけてくれと。せめて声を…頼む」
モラレスの私宅の牢舎に拉致監禁されているゴメスが、ベンハミンに漏らした絶望的言辞である。
ゴメスは、檻(おり)に近づいたベンヤミンの顔に手を伸ばし、触れようとする。
その時、ゴメスは絞り出すように、ベンハミンに対して、このように哀訴したのだ。
思うに、我が国でも、その導入が検討されている「絶対的終身刑」(重無期刑)。
生涯にわたって、自らが犯した罪を償うことが約束されているにも拘らず、受刑者の人格崩壊を危惧するという反対論もある。
しかし、惨(むご)いまでの強姦殺人事件を犯した男が、司法権力の恣意的発動によって釈放された理不尽な現実に遮(さえぎ)られ、無力化されたモラレスにとって、もう、それ以外の方略しかなかった。
 |
| ベンハミンの家の前で、ゴメスが現れるのを待つモラレス |
 |
| 現れたゴメスを視認し、射殺するに至るが、実際は私宅監置で「終身刑」を科していく |
 |
| モラレスが負う生涯のトラウマ |
仮に「絶対的終身刑」を採用し、仮出所がなくても、独房に収監される受刑者には1時間程度の運動(高齢者には運動機能訓練)があり、様々な刑務作業(無期懲役の場合)も可能であるから、新聞・週刊誌などの読書、食事の楽しみも奪われることもないと思われるので、受刑者の人格崩壊を必至にするとは言い切れないだろう。
 |
| 絶対的終身刑(イメージ画像) |
そして何より、事件の被害者への贖罪的な指導の実践などを通して、専門家や刑務官らとの言語交通が遮断されることもないのである。
この現実を考えれば、言語交通を奪われることは、人間性の一切を削り取られる「廃人化」と同義であると言っていい。
一言で表現すれば、究極の拷問である。
「廃人化」し、残忍な〈死〉に屠(ほふ)られていく時間を待つだけの、終わりなき究極の拷問なのだ。
これが、ゴメスに約束された〈生〉の全てなのである。
「殺してどうなる。僕が捕まる。奴は死によっては解放されるが、僕は50年、塀の中で暮らす。ごめんだ。奴が終身刑になれば、それでいい」
「気が治まる?奴を暴行し、殺すのか?違うだろ。注射で永遠に眠らせるだけだ。羨ましいくらいだ…犯人には、長生きして欲しい。空虚な日々を生きて欲しい」
ベンハミンに対して放ったモラレスの憎悪の言辞の全てが、ここに凝縮されている。
注射で永遠に眠らせるアルゼンチンの死刑制度(2009年に完全廃止)ではなく、終身刑による空虚な日々を生きていくこと。
だから、永遠に消えない「至福の新婚生活」を奪った男への復讐譚は、言語交通を奪い尽くすという酷薄なる風景を可視化させたのである。
「終身刑ですよね」
男はベンハミンに、こう言い放った。
「赦す」ことをかなぐり捨てた男のグリーフ(悲嘆)は、なお延長されていて、自己完結していないのだ。
【グリーフワークとは、悲嘆の当事者が辿る心的過程のことで、「衝撃」⇒「喪失」⇒「閉じこもり」⇒「再生」というようなプロセスがあると言われる】
 |
| グリーフワーク |
それは同時に、喪ってはならない新妻を喪った男の、喪った新妻に対する、それ以外にない鎮魂の儀礼であるのかも知れない。
些か歪んでいるが、鮮烈なまでに強靭な男の〈愛〉の情景を目の当たりにして、もう一人の男が駆動していく。
ベンハミンである。
過去に覆い尽くされて動けず、「怖い」とさえ記したベンハミンは、小説によってしか想いを言語化できなかった時間の総体を束ね、それを超克させていくのだ。
 |
| 小説の中の世界/別離の悲哀(3枚の画像) |
モラレスの心情にシンクロさせてきた男が今、自己を総括し、近未来の時間の向こうに、自己の物語のサイズを目一杯広げ、彩色を施していくのである。
 |
| イレーネに対する自らの愛を、モラレスに投影した典型的な画像 |
恐怖突入である。
先(ま)ず、「サバイバーズギルト」(生存者罪悪感)を浄化させねばならない。
パブロを死なせたことに対する自責の念の重みで、潰れそうになっている自我を立て直す。
 |
| ベンハミンの小説の中での、死の直前のパブロのイメージ |
長い年月を要したが、拭い難いトラウマによって足踏みしていたパブロの墓参を遂行した。
そして今、最後の、最大にして、澱み続けていた想いの束を弾き出す。
「いつもイレーネのことを考えてる。彼女の結婚願望は筋金入りだ。デスクの上は、花嫁雑誌でいっぱいだ。婚約パーティーも開いた。だがお前は、奇跡を待ち続けている。なぜだ」
こんな風に、愛すべき同僚・パブロから揶揄され、逃亡していた弱さを突き抜けていくのだ。
「なぜ無視し続けるの?私を避けないで。同じ世界の人間よ」
「だといいが。これ以上、よそう」
「何を?」
「君はエンジニアの彼と結婚する身だ」
「妬いてるの?」
「まさか。幸せを願ってるよ」
小説での別離の際の会話だが、苛立つイレーネからの愛を受容できない男の弱さの根柢には、ステータスに起因する劣等感が渦巻いている。
「彼女は法学博士だが、お前は高卒だ…生きる世界が違うんだ」
ロマーノにここまで嘲弄(ちょうろう)され、返すべき言葉の何ものもなかった。
「彼女に触れたら殺す」
ゴメスがイレーネが殴られた際に、放ったベンハミンの堂々たる言辞である。
この一言で明瞭なのに、その先は進めない。
イレーネが「扉を閉める」用意をして待っているのに、逃げてしまうのだ。
これが25年間もの澱(おり)と化しているから、結婚にも頓挫する。
この澱(おり)を溶かさない限り、もう、一歩も先に進めなかった。
全て、グリーフ(悲嘆)を延長させていたモラレスのお蔭である。
理不尽な罪を犯しても、罪に問わない腹黒の男たちに代わって、自ら終身刑を断行するモラレスの異様とも思える〈現在性〉を視認したことが推進力と化し、一人称の映画の主人公・ベンハミンは駆け走っていくのだ。
「扉を閉める」用意をして待っている、最愛の女性に向かって。
【1946年 ペロン政権の成立⇒1973年 軍部介入など変遷の後、再度ペロン大統領が就任⇒1976年 クーデターにより軍事政権成立】
これは、外務省のアルゼンチンの略史だが、簡単に書けば、以下のように要約できる。
―― 「正義党」と呼ばれるアルゼンチンの政党がある。
「ペロン党」という別称で知られるアルゼンチンの最大政党=国民政党である。
軍事クーデターによって、創立者のフアン・ペロン(当時の大統領)が追放されたにも拘らず、この人物が大統領に復帰する1973年まで非合法化された「正義党」が、一貫して大衆の支持を得られたのは、極右から左派に及ぶオールラウンドな思想フィールド(中道左派及び、中道右派)を包含する曖昧さと無縁ではない。
 |
フアン・ペロン(ウィキ)
映画の時代背景は、フアン・ペロンの第三夫人で、世界初の女性大統領として有名なイサベル・ペロンの統治下でのこと。
 |
| イサベル・ペロン |
この時代、左翼ゲリラや軍部との抗争激化で治安の極端な悪化が露呈され、イサベルもまた、逮捕・収監・失脚後も、ボディーガードなしではいられない余生を過ごしたと言われる。
映画には、このイサベルが大統領時代に、リリアナ強姦殺人の犯人ゴメスがイサベルのボディーガードに転じて、テレビ画像に映っていたことで、時代背景が判然とするだろう。
(2021年12月)





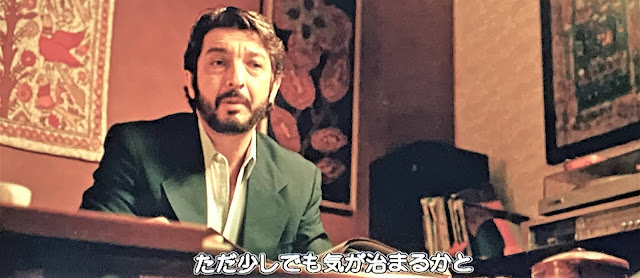


































































































0 件のコメント:
コメントを投稿